入居者トラブルの実例と対処法20選|賃貸経営者・オーナー必見の完全ガイド
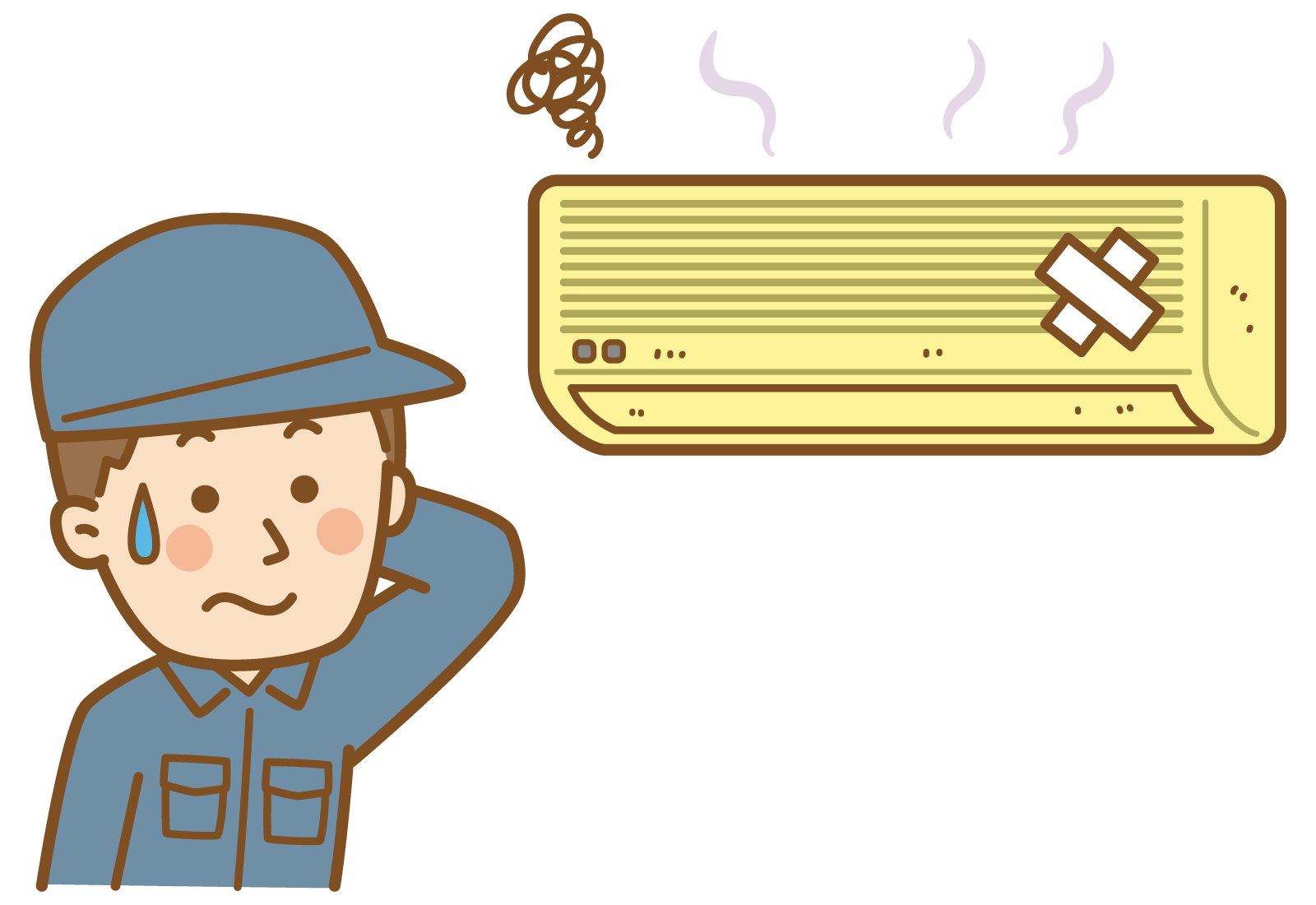
賃貸経営において「入居者トラブル」は避けて通れない重要課題のひとつです。どれだけ入居審査を慎重に行っていても、実際に生活が始まると、さまざまな問題が徐々に表面化してくるものです。たとえば、隣人との騒音トラブルやゴミ出しのマナー違反、ペットの無断飼育、家賃の滞納といった比較的身近な問題から、無断転貸や民泊利用、孤独死、犯罪の疑い、SNSでの風評被害など、管理者では想像もしていなかったような深刻な事態に発展するケースもあります。
こうしたトラブルに適切に対応できるかどうかは、賃貸経営の安定性と信頼性に大きく関わります。対応を誤れば、他の入居者からの信頼を失い空室リスクが高まるだけでなく、法的なトラブルや損害賠償請求に発展することもあり得ます。
そこで本記事では、実際に現場で多く見られる入居者トラブルの【実例】を20項目に厳選し、それぞれに対する【具体的な対処法】を丁寧に解説しています。単なる理論ではなく、現実に基づいた対応の流れや注意点も押さえているため、すでに物件を所有している賃貸オーナーや不動産管理者の方はもちろん、これから賃貸経営を始めようと考えている初心者の方にとっても必読の内容です。
トラブルは「起きてから慌てる」のではなく、「起きる前提で備える」ことが大切です。ぜひ本記事を参考に、賃貸経営のリスクを最小限に抑えるための知識と実践力を身につけてください。
1. 騒音トラブル
よくあるケース
・深夜にテレビや掃除機を使用することで音が建物全体に響き渡り、特に木造や築年数の古い物件では壁が薄く、近隣住民に不快感を与えることがあります。
・子どもが室内を走り回ったり飛び跳ねたりする足音が階下に響き、育児世代と高齢者世代の生活リズムの違いからトラブルになることも多いです。
・楽器の演奏や複数人でのホームパーティーなど、生活の一部であっても周囲からすれば騒音に感じるケースがあります。

対処法
騒音問題は感覚に個人差があるため、まずは発生時間・音の種類・頻度などを具体的に記録することが重要です。その上で管理者側から該当入居者に対して、匿名または書面での注意喚起を行います。改善が見られない場合は、「契約書上の迷惑行為禁止条項」に基づき是正通知を発行し、最終的には契約解除や退去勧告など法的対応を検討します。
2. ゴミ出しマナー違反
よくあるケース
・家庭ごみの分別ルールを守らず、可燃ごみに瓶や缶、プラスチックなどが混入して回収されず、ゴミが放置されて悪臭の原因となるケースがあります。
・収集日以外にゴミを出してしまい、数日間そのまま放置されることで害虫やカラスなどの被害が発生し、他の入居者の迷惑になることも。
・粗大ごみを管理者に無断で共用部に放置することで、避難経路を塞ぐ危険や建物の景観を損なう問題が生じます。

対処法
まずは建物内の掲示板やエントランスにゴミ出しのルールを明確に掲示し、全入居者に周知を徹底します。違反が確認された場合は、該当者に個別で注意を促し、それでも改善されない場合は原状回復費(清掃費など)を請求するなど、段階的な対応を取ります。特にルール違反が常習的で悪質な場合は、契約違反として強制退去を検討する必要があります。
3. 家賃滞納
よくあるケース
・月初の家賃が期日を過ぎても入金されず、管理側が連絡をしてようやく支払うという遅延が常態化している入居者がいます。
・2ヶ月以上にわたって家賃の支払いが止まり、本人との連絡も取れなくなった場合、保証会社や連帯保証人への通知・対応が必要になります。

対処法
家賃滞納は早期対応が鍵です。1日でも遅れが出たら電話やLINE・メールなどで即時確認を行い、1ヶ月を超えるようであれば内容証明郵便での催促を送ります。保証会社が付いている場合は早めに報告し、支払い代位弁済を進めます。それでも支払いがなければ、明渡し訴訟や強制執行も視野に入れ、契約解除に向けた法的手続きを進める必要があります。
4. ペットの無断飼育
よくあるケース
・ペット禁止の物件で猫や小型犬を内緒で飼っており、ベランダでの鳴き声や室内の臭いが外に漏れて、近隣住民からの苦情につながります。
・共用部やエレベーターにペットの毛や糞尿の臭いが残っていたり、マーキングなどがあったりして衛生面や印象に影響を与えます。

対処法
ペットの無断飼育は契約違反にあたるため、まずは写真や目撃証言などの客観的な証拠を集めることが重要です。そのうえで、書面による注意・飼育中止の要請を行い、改善されない場合は損害賠償請求や契約解除、退去要求を検討します。再発防止のためにも、契約書に具体的なペナルティ条項を明記しておくと効果的です。
5. 共用部分の私物放置
よくあるケース
・自転車や傘、ゴミ袋、ベビーカーなどを共用廊下や階段に置きっぱなしにしており、通行の妨げや景観の悪化につながっています。
・火災や地震など災害時の避難経路を塞いでしまうリスクもあり、安全上の問題としても放置できない事態になります。
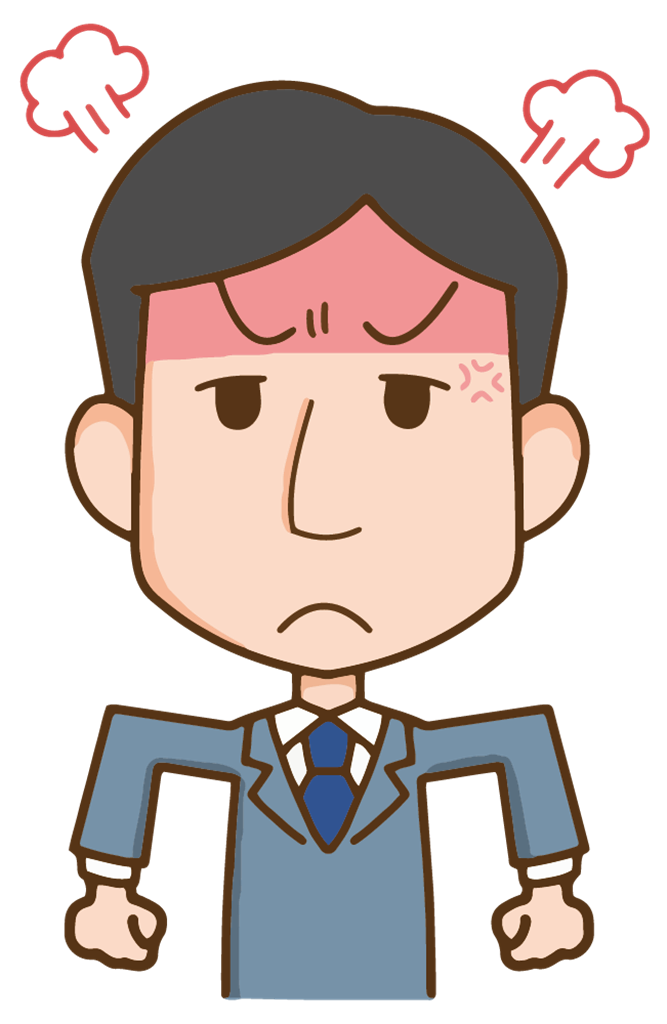
対処法
まずは共用部の放置物に対して警告文を貼り出し、一定期間内の撤去を求める通知を行います。改善が見られない場合は「撤去予告文」を掲示し、それでも無視される場合は管理者の判断で処分することが可能です。契約書に「共用部私物放置禁止」の条項を入れておくことで、入居時からの予防にもなります。
6. 無断同居・転貸
よくあるケース
・契約者以外の人物(恋人・友人・親族など)が長期間居住しており、正式な手続きを取らずに無断で同居しているケースがあります。
・さらに悪質な例では、契約者が他人に部屋を又貸しして収益を得ているなど、完全な契約違反に該当するケースもあります。
対処法
定期的な物件巡回や他の入居者からの通報をもとに事実関係を確認し、無断同居や転貸が判明した場合は速やかに是正を求めます。書面による指導通知を出したうえで、従わなければ契約解除・明渡し請求を行います。必要であれば弁護士とも連携し、法的手続きを検討します。
7. 契約違反の民泊利用
よくあるケース
・入居者がAirbnbなどの民泊サービスを使い、部屋を不特定多数に短期貸ししていたことが発覚するケースがあります。
・出入りが激しく、スーツケースの音や他言語での会話などにより、他の入居者の生活環境が大きく損なわれることもあります。

対処法
民泊は契約書で明確に禁止されていることが多いため、民泊サイトにて対象物件を特定できた場合は、証拠として記録しておきます。違反が確定した段階で即時の中止命令を出し、改善がなければ損害賠償請求および強制退去を行います。物件の評判にも関わるため、迅速かつ断固とした対応が求められます。
8. 夜間の生活騒音・振動
よくあるケース
・夜中に洗濯機や掃除機を使うことで振動や音が階下に響き、特に深夜の時間帯は大きな迷惑行為と受け止められやすいです。
・重低音の音楽やゲームの効果音、ホームシアターなども壁を通して響き、音に敏感な入居者からの苦情が多発します。
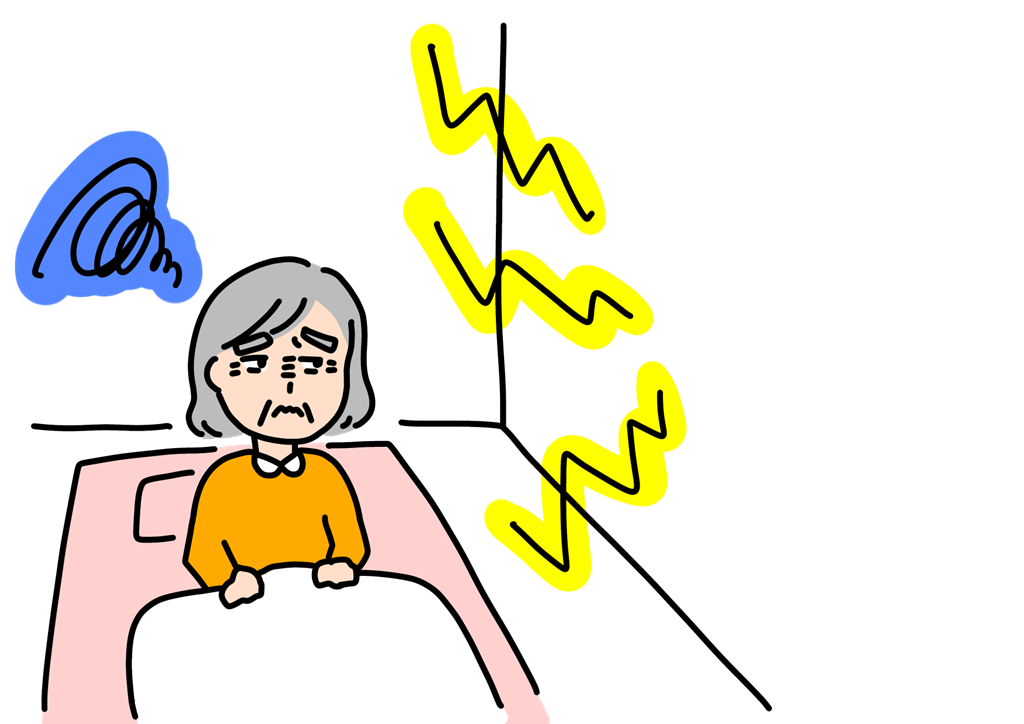
対処法
音の種類や時間帯を記録し、「夜間(22時以降)の生活音に対する配慮」を求める文書を発行します。再発防止には、音響測定機器による客観的な記録も有効です。特にリピーターや改善意思が見られない場合には、契約書に基づく指導や契約解除を視野に入れましょう。
9. 悪臭・換気トラブル
よくあるケース
・キッチンの換気が不十分で料理の油臭やタバコの煙が隣室に流れ込むことで、においトラブルが発生するケースがあります。
・ペットの臭いや芳香剤の香りが強すぎて、窓越しや換気扇から隣接住戸へ移動し、クレームにつながることもあります。

対処法
原因が設備にある場合は、まず専門業者による点検・修理を行い、換気機能の正常化を図ります。入居者の生活習慣に起因する場合は、状況を丁寧に説明し、改善要望を出すとともに、あまり強く責めないバランスが重要です。対応が難航する場合は契約違反としての警告も検討します。
10. 近隣住民との衝突
よくあるケース
・隣人同士の挨拶やマナーの違い、子ども同士のケンカが発端となって大人の間で口論や暴言にまで発展するケースがあります。
・些細な行き違いやトラブルがエスカレートし、住民同士が顔を合わせるのを避けるようになるなど、住環境に悪影響が出ることも。

対処法
管理者は中立な立場を保ちつつ、双方の主張を丁寧にヒアリングし、感情的な応酬になる前に仲裁に入ることが大切です。必要であれば自治会や弁護士と連携し、第三者を交えての話し合いや文書による再確認も検討します。住民間の信頼を回復するためには、冷静で迅速な対応が不可欠です。
11. 駐車場・駐輪場の無断使用
よくあるケース
・契約されていない車両が無断で駐車場を使用し、正規の契約者が駐車できない状況が続き、トラブルに発展することがあります。
・駐輪スペースが限られているにもかかわらず、無許可のバイクや自転車が長期間放置されて通行の妨げや盗難の不安を招くことも。
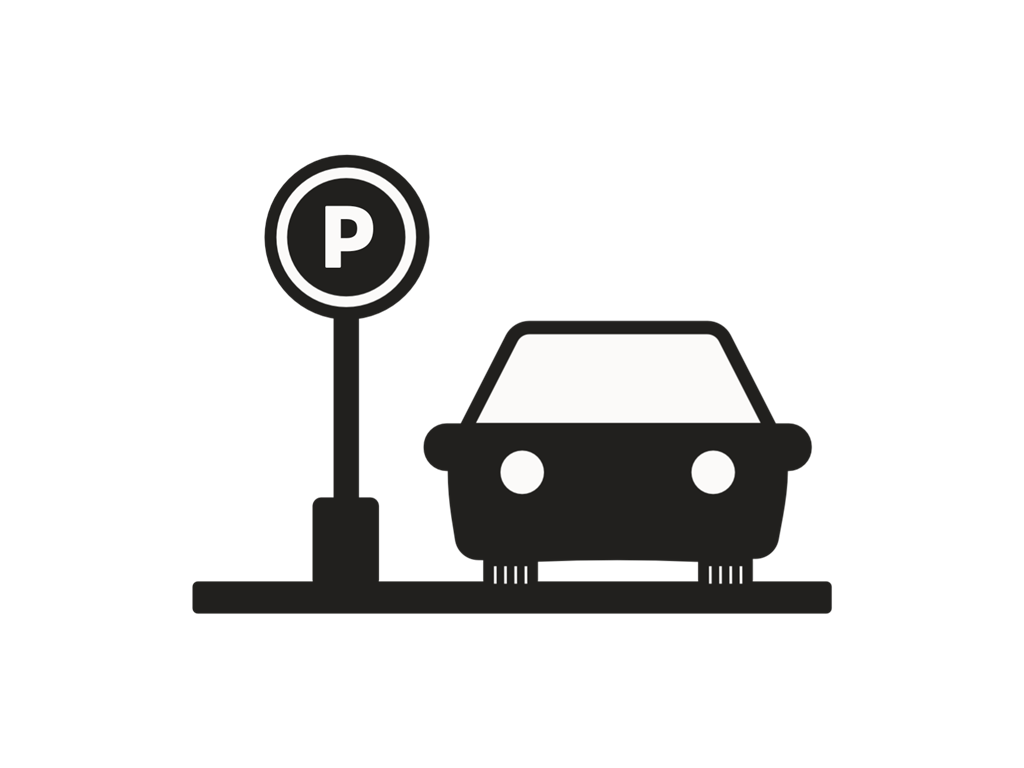
対処法
まずは無断で停められている車両のナンバーや特徴を記録し、注意喚起の貼り紙を掲示します。それでも改善がない場合は、警察やレッカー業者と連携して移動措置をとることが可能です。駐輪に関しては、契約者以外の使用を禁止する旨を契約書や掲示板で明示し、改善がない場合は撤去や罰金の対象とすることも視野に入れます。
12. 契約者本人の所在不明
よくあるケース
・ポストに郵便物が溜まり、連絡が取れないまま長期間姿を見せない入居者がいる場合、事故や失踪の不安が高まります。
・急な退去や夜逃げのような形で部屋が放置され、家賃も未払いのまま、契約者本人との接触が一切できない状態になることもあります。
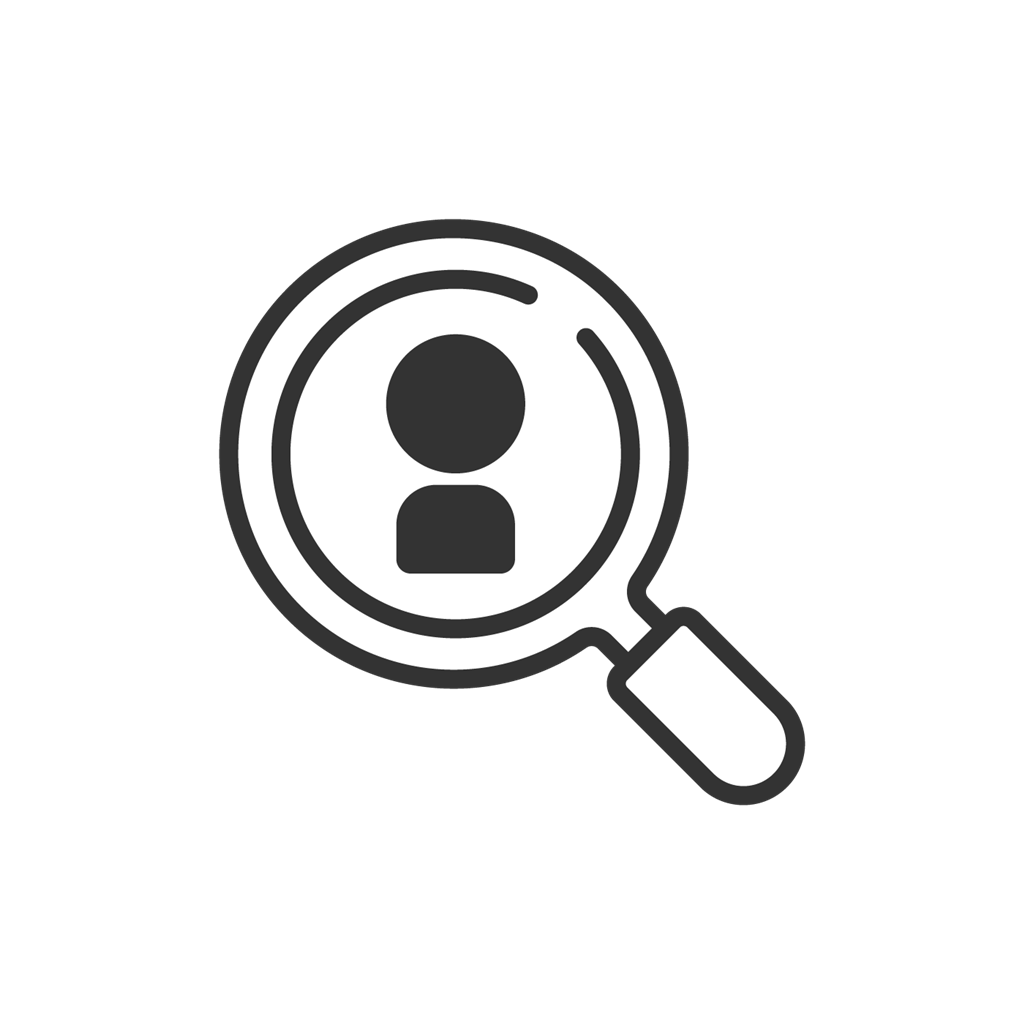
対処法
まずは緊急連絡先や連帯保証人に連絡を取り、本人の安否や所在を確認します。必要に応じて警察に通報し、安否確認を依頼することもあります。放置された室内に異常が見られる場合は、法的手続きを経て室内の確認や明渡し訴訟を進めます。勝手な入室はトラブルの原因となるため、必ず法律に則った対応を行うことが重要です。
13. 薬物・犯罪の疑い
よくあるケース
・入居者の部屋に不審な人物が出入りしていたり、夜間に大きな音や叫び声、異臭などが確認され、薬物使用や犯罪行為の疑いが生じます。
・室内から漂う化学薬品のような匂いや、壁に異常なシミや破損が見られた場合には、危険薬物の製造などの可能性も否定できません。

対処法
このような事案は管理者レベルでの対応は危険を伴うため、速やかに警察に通報し、事実確認や捜査を依頼することが第一です。証拠となる写真や目撃情報は記録に残しておきましょう。安易な対話や自己判断による注意は、トラブルや報復のリスクがあるため避けるべきです。安全第一で、専門機関と連携して対応してください。
14. 高齢入居者の孤独死
よくあるケース
・高齢者の入居者と数日間連絡が取れなくなり、ポストの郵便物の滞留や室内からの異臭などで異変に気づくことがあります。
・孤独死が発生した場合、遺体の発見が遅れると特殊清掃や原状回復に多額の費用がかかり、次の入居にも大きな影響を与えます。

対処法
まずは緊急連絡先や家族、保証人に連絡し、本人の安否を確認します。それでも連絡がつかない場合は、管理者や警察立ち会いのもと、法的手続きを経て室内確認を行います。事故後の処理としては、特殊清掃・遺品整理・告知義務の対応・家財の撤去・保険申請などを適切に進める必要があります。事前に見守りサービスの導入や家族との連携体制を整えておくと安心です。
15. 退去時の原状回復トラブル
よくあるケース
・退去時の室内に壁紙の破れやフローリングの大きな傷があるにもかかわらず、入居者が「経年劣化」と主張して負担を拒否することがあります。
・敷金の返還金額を巡って、国のガイドラインを無視した一方的な主張で口論や法的トラブルになるケースもあります。

対処法
退去時には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って、適切な費用負担を判断します。入居時の写真・状態記録・契約書の内容を明示し、必要があれば第三者による見積もりを提示します。感情的な対応は避け、冷静かつ論理的な説明を心がけましょう。トラブル防止のためにも、入居時の説明を丁寧に行うことが大切です。
16. カビ・水漏れへの過剰クレーム
よくあるケース
・壁や天井に軽度のカビが発生した際に「建物の不備」だと過剰に責任を追及されたり、数万円以上の補償を要求されることがあります。
・水漏れが室内に多少生じた場合でも、過剰な精神的苦痛や家具への損害補償を求める入居者も稀に見受けられます。
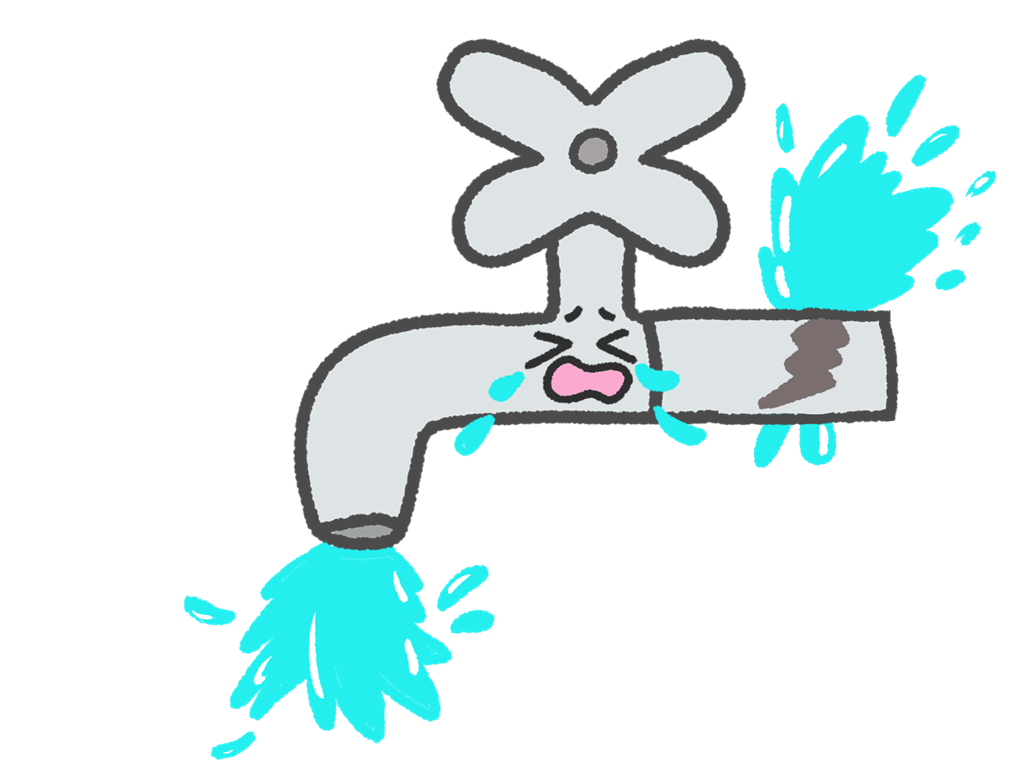
対処法
まずは現地調査を行い、建物構造や換気状況、入居者の使用環境などを総合的に判断します。責任の所在が明確であれば修繕を行い、過剰請求や不合理な補償要求に対しては、専門業者の診断書や法的な根拠をもって丁寧に対応します。予防策として、入居時に湿気対策や使用注意点を説明しておくことも有効です。
17. 誤解による訴訟・法的トラブル
よくあるケース
・入居者が「説明を受けていない」「聞いていない」と主張し、契約の内容や条件を巡って訴訟に発展するケースがあります。
・SNSや口コミサイトに悪意ある投稿をされ、風評被害や営業妨害につながる事態になることもあります。

対処法
トラブルの多くは「言った・言わない」の水掛け論に発展するため、すべてのやり取りを文書またはLINE・メールで記録しておくことが重要です。契約書や重要事項説明書の写しも必ず保存し、相手にもしっかり交付しておきましょう。SNSでの誹謗中傷があった場合は、スクリーンショットを保存し、場合によっては法的措置を取ることも検討します。
18. 他入居者への嫌がらせ行為
よくあるケース
・隣室の入居者から「監視されている」「じっと見てくる」など精神的な不安を訴える声が寄せられ、直接対話が困難になるケースがあります。
・ベランダにゴミを投げ込まれる、郵便受けを荒らされるなどの物理的な嫌がらせ行為が起きることもあります。

対処法
まずは被害者の訴えを丁寧に聞き取り、証拠となる写真や映像、日時の記録を確認します。加害者が明確な場合は、警告文の送付や面談を通じて改善を促し、それでも行動が改善されない場合には契約解除や強制退去の手続きも視野に入れます。トラブルが悪化する前に、専門家や弁護士とも相談しながら対応しましょう。
19. 夜逃げ・突然の連絡断絶
よくあるケース
・家賃の支払いが滞りがちだった入居者が突然連絡を絶ち、部屋に荷物を残したまま行方不明になるケースがあります。
・鍵が返却されず、室内の電気・ガス・水道が止まっており、生活感がない状態が続くことで発覚することが多いです。

対処法
まずは保証会社や連帯保証人に連絡を取り、状況を共有します。一定期間経過後、内容証明や明渡し訴訟、残置物処理手続きに移行します。勝手な室内立ち入りや荷物の処分は法的リスクがあるため、法的手順に従って対応することが原則です。保証会社を活用しながら、入居時の契約内容を踏まえた準備が重要です。
20. 管理会社への過度なクレーム
よくあるケース
・些細なことでも深夜や休日に何度も電話をしてきたり、対応が遅いと激高して怒鳴り散らすような入居者がいます。
・SNSやクチコミサイトで実名や社名を挙げて誹謗中傷を書き込まれるなど、業務妨害に発展するケースもあります。

対処法
まずは感情的にならず、対応内容はすべて記録・文書化しておくことが大切です。電話での応対もなるべく録音し、証拠として保管します。常識的な範囲を超えるクレームが続く場合は、弁護士に相談し「業務妨害」「名誉毀損」などの法的措置も視野に入れて対応します。社内でも一人で抱え込まず、複数人で対応できる体制を整えておくことが重要です。
まとめ|トラブルの「事前対策」と「冷静対応」が賃貸経営を守るカギ
入居者トラブルは、賃貸経営を行ううえで避けて通れない現実です。騒音やゴミ出しのマナー違反から、無断同居・家賃滞納、さらには犯罪行為や孤独死まで、あらゆる場面で突発的に問題が発生する可能性があります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、入居前の審査や契約書の精度向上、入居時の丁寧な説明、定期的な巡回とコミュニケーションなど、オーナーや管理会社による「事前の備え」が非常に重要です。また、実際に問題が発生した際には、記録を残しながら冷静かつ段階的に対応していくことが、感情的な対立や法的トラブルを防ぐポイントになります。
さらに、保証会社や弁護士との連携体制を整えておくことは、深刻な事態に発展したときのリスク軽減に繋がります。高齢者の孤独死や夜逃げ、SNSでの風評被害など、近年のトラブルは複雑化しており、専門的な知識とネットワークが不可欠です。
本記事で紹介した20のトラブル事例と対処法を参考に、今後の賃貸管理に役立てていただければ幸いです。オーナー様・管理会社様が「信頼される賃貸経営者」であるために、備え・対話・記録・法的根拠を常に意識し、リスクに強い運営を目指しましょう。
迷ったらプロに相談してみませんか?
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。
小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!




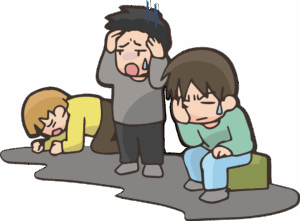






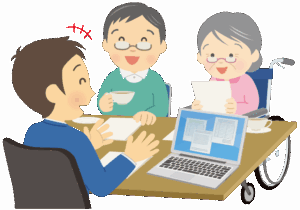
コメント