住宅ローン事前審査と団体信用生命保険|否決判例に学ぶ注意点

マイホーム購入でほとんどの人が利用する住宅ローン。審査には「事前審査」と「本審査」があり、団体信用生命保険(団信)の告知は通常、本審査で行われます。
ところが、団信の否決が原因でローンが実行されず、融資利用特約による解除も認められなかった判例が存在します。東京地裁平成10年5月28日判決です。実はこの事案は、団信否決だけでなく、共同買主が連帯保証人にならなかったことも裁判所の判断に大きく影響しました。
この記事では、この判例をわかりやすく紹介しつつ、事前審査と本審査の違い、団信の重要性、そして契約トラブルを避けるための具体的な対策を解説します。
住宅ローン審査の基本|事前審査と本審査
事前審査とは「人」の一次チェック
事前審査(仮審査)は、購入希望者が住宅ローンを利用できるかどうかを、金融機関が大まかに確認する段階です。
チェックされるのは主に次のような項目です。
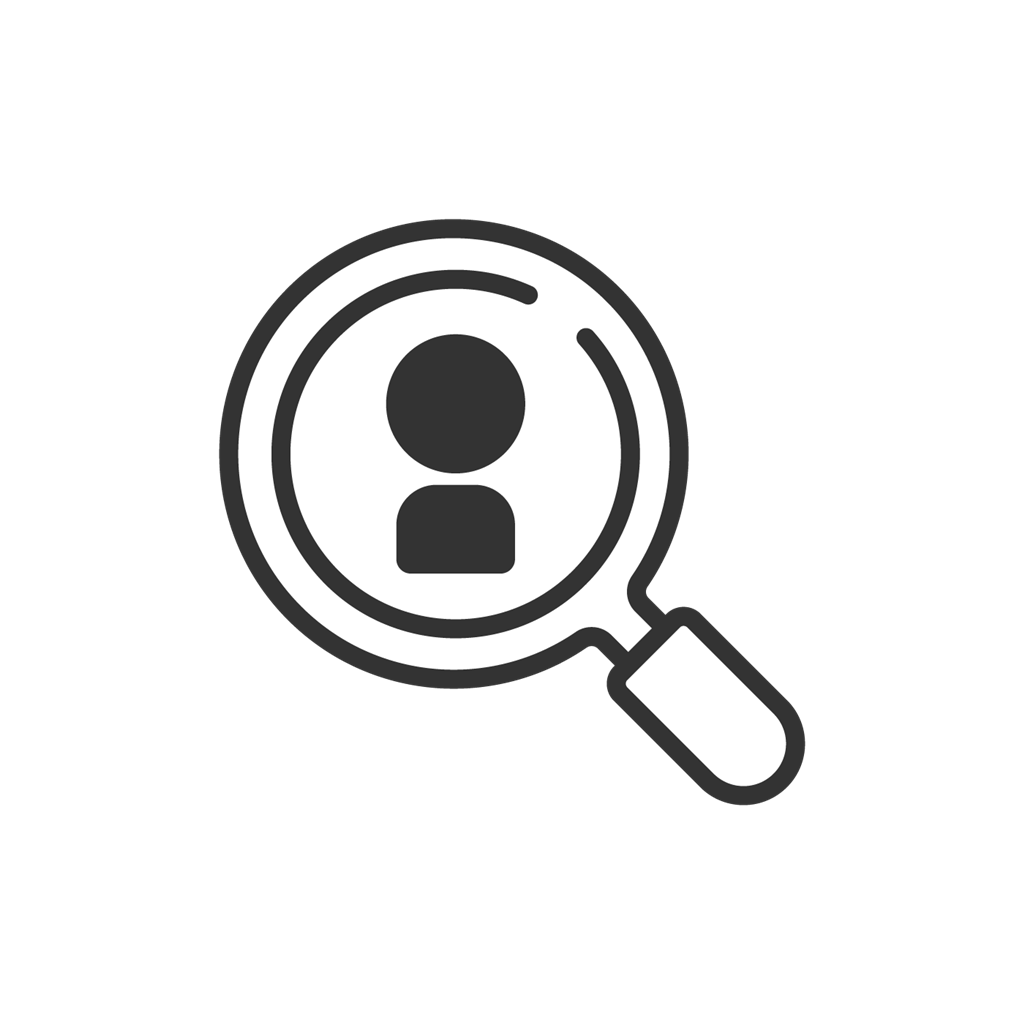
年収水準
前年の源泉徴収票や確定申告書の数値を基に、年収と借入希望額のバランスが適正かどうかを確認します。
一般的には「年収の7〜8倍程度まで」が目安とされますが、実際は勤務形態や他の借入状況によって調整されます。
勤務先・勤続年数
上場企業や公務員など安定した勤務先であれば評価は高く、勤続3年以上が目安とされます。ただし近年は転職が一般化しているため、職種や業界が継続していれば2年未満でも認められるケースがあります。
他の借入状況
自動車ローンや教育ローン、カードローンなどの残債もすべて確認されます。返済比率(返済負担率)が一定の範囲内に収まっているかどうかが重視され、複数の借入がある場合は不利になることもあります。
信用情報(CICやJICC)
過去の延滞履歴や債務整理の有無、クレジットカードの利用状況など、個人の信用情報機関に登録されている内容も参照されます。延滞や強制解約の履歴があれば、事前審査の時点で否決される可能性が高まります。
なお、この段階では物件については価格や所在地などの概要程度しか見られません。
詳細な担保評価や建築的な適法性のチェックは本審査に回されます。
また、団体信用生命保険(団信)についても通常は告知不要で、ここでは「健康状態」による足切りは行われないのが一般的です。
したがって、事前審査はあくまで「この人にローンを貸す可能性があるか」を簡易的に確認するものであり、通過したからといって安心できるものではありません。
むしろ「購入の第一関門を通過したにすぎない」と考えるべきであり、本審査で詳細な書類審査や団信加入可否、物件評価が待っていることを意識しておくことが重要です。
本審査は「人+物件+団信」の最終チェック
本審査では、住宅ローンの融資を実行できるかどうかを金融機関が最終的に判断します。
事前審査よりも提出書類や確認項目が多く、審査基準も厳格になります。
具体的には、以下のような観点から詳細なチェックが行われます。

借主の詳細属性
源泉徴収票や確定申告書、課税証明書といった公的な収入証明の提出が必要となります。
また、勤務先への在籍確認や勤続年数、雇用形態の安定性なども重視され、単に「年収」だけでなく「将来にわたり返済を継続できるか」が評価されます。
物件の担保評価
融資対象となる物件の登記簿謄本や建築確認資料を基に、法的に問題がないか(違法建築や未登記部分の有無)、耐震性や管理状況は適正かなどを確認します。
さらに、不動産鑑定的な観点から「担保価値(金融機関が担保として認める評価額)」が算定され、借入希望額とのバランスが審査されます。評価額が低い場合は、希望額どおりの融資を受けられないこともあります。
団信告知書による健康状態の審査
借主は団体信用生命保険(団信)の加入にあたり、健康状態を告知します。
高血圧や糖尿病、心疾患、がん、精神疾患などの既往歴や治療歴は慎重にチェックされ、リスクが高いと判断されれば加入を断られることもあります。
団信加入が不可の場合、その金融機関ではローン自体が成立しないケースが大半です。
このように本審査では、「人の信用力」+「物件の担保価値」+「団信加入可否」という三つの柱を総合的に判断します。つまり、安定した収入があり信用情報に問題がなくても、物件の評価が低かったり団信に加入できなければ融資は実行されません。
逆に、物件評価や団信に問題がなくても、収入や勤務状況に不安があれば否決される可能性があります。本審査を通過してはじめて、住宅ローンの実行が確定するのです。
団信の役割と健康告知の重要性
団信とは住宅ローンの「安全装置」
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン契約者が返済中に死亡したり高度障害状態になった場合、残っているローン残債を保険金で完済してくれる仕組みです。
金融機関にとっては貸し倒れを防ぐための重要なリスクヘッジとなり、借主にとっては「万一のときに家族がローン返済に苦しむことがない」という大きな安心材料になります。
実際、団信に加入していれば、遺族は自宅を失うことなくそのまま住み続けられるため、住宅ローンの安全装置として欠かせない存在です。

このため、民間金融機関が扱う住宅ローンの多くでは団信加入が必須条件とされています。健康状態などの理由で団信に加入できない場合、原則としてその金融機関からの融資は実行されません。
つまり、借主がいくら高収入で返済能力に問題がなくても、団信に通らなければローン契約自体が成立しないのです。
したがって団信審査は、収入や勤務先を確認する事前審査や、本審査での物件担保評価と並ぶ、住宅ローン審査における「最後の関門」といえます。
特に健康状態に不安を抱えている人にとっては、団信の可否が融資の成否を決める決定的なポイントとなるため、軽視できない極めて重要なプロセスです。
告知義務と審査リスク
団信に加入する際には、所定の「告知書」に健康状態や過去の病歴を正確に記入する必要があります。審査対象となるのは、高血圧や糖尿病といった生活習慣病、心疾患や脳疾患、がんの治療歴などの大きな病気だけではありません。
緑内障や網膜剥離などの眼の病気、喘息や慢性気管支炎といった呼吸器疾患、肝炎・肝機能障害などの肝疾患、潰瘍性大腸炎などの消化器疾患、あるいはうつ病や統合失調症などの精神疾患も告知の対象となり、審査ではリスクありと判断される可能性があります。
たとえ日常生活に大きな支障がなくても、将来的なリスクがあると見なされる病気は、団信加入において慎重に審査されます。例えば緑内障は失明リスクがあるため、告知次第では「通常団信否決」とされる場合もあります。
同様に、軽度のうつ病や過去の手術歴も、「完治しているか」「投薬中か」といった点によって判断が分かれます。
ここで虚偽記載や告知漏れをすると、契約が解除されたり、万一のときに保険金が支払われない事態になりかねません。つまり、告知は融資実行時の審査をクリアするだけでなく、将来の保障を有効に保つためにも極めて重要です。
健康状態によっては通常の団信に加入できない場合もありますが、その際には保険料を割増してでも加入できる「ワイド団信」を利用する、あるいは団信加入が任意のフラット35を選択するなどの選択肢があります。
こうした制度を理解しておくことで、告知によって団信が否決されても柔軟に対応できるでしょう。
東京地裁平成10年5月28日判決に学ぶ
事案の概要
買主は事前審査を通過したことで「これでローンは大丈夫だろう」と安心し、そのまま売買契約を締結しました。
しかし本審査に進んだ段階で、初めて団信告知書に健康状態を記入し、高血圧を抱えていることを申告しました。
その結果、保険会社から団信への加入を認められず、住宅ローンの実行ができない事態に陥ってしまいました。

さらに状況を悪化させたのが、共同買主の一人が金融機関から求められた連帯保証人になることを拒否した点です。本来、共同購入であれば互いに協力して融資手続きを進める必要がありますが、その協力が得られなかったため、金融機関はローン審査自体を完了させることができませんでした。
こうした経緯から、買主は「ローンが通らなかった以上、契約書に記載された融資利用特約を根拠に契約を解除できるはずだ」と主張しました。しかし裁判所は、融資不成立の原因は団信否決や連帯保証人拒否といった買主側の事情にあると判断し、融資特約による解除を認めませんでした。
(※この判例は不動産関連専門サイト・法律解説記事にて紹介されています)
裁判所の判断
裁判所は、今回の融資不成立に至った原因を大きく二つに整理しました。
一つ目は、買主が本審査において健康状態を申告した結果、団信への加入が認められなかった点です。これは買主自身の持病や既往歴といった個別の事情によるものであり、金融機関側の都合によるものではありません。
二つ目は、共同買主の一人が金融機関から求められた連帯保証人になることを拒否し、融資手続を円滑に進めるための協力義務を果たさなかった点です。本来であれば、共同で購入する以上、互いに協力してローンを成立させる努力をするべき立場にあるのに、その協力を欠いたことが融資不成立の大きな要因となりました。
裁判所はこれら二つの事情を総合的に評価し、「融資不成立は金融機関の責任ではなく、買主側の責任によるもの」と判断しました。その結果、契約書に記載されていた融資利用特約による解除は適用できないとされ、買主は特約解除を主張することが認められなかったのです。
この判例が示すこと
重要なのは「団信否決だけが理由ではなかった」という点です。
- 通常であれば、団信否決は融資不承認に含まれ、ローン特約で解除できるケースが多い。
- しかしこの事案では「共同買主の協力拒否」という重大な事情が重なり、裁判所は買主側の責任と認定。
- 結果として、契約解除は認められず、買主は手付放棄などの不利益を負うことになりました。
実務への教訓|健康面に不安のある人は団信告知は事前審査時に
健康状態は事前に正直に申告する
団信告知は原則として本審査のタイミングで行われるのが一般的です。
しかし、高血圧や糖尿病といった持病、過去の手術歴や通院歴など既往症がある場合には、いざ本審査の段階で告知した結果「団信に加入できない」と判断され、ローンそのものが不成立になるリスクがあります。
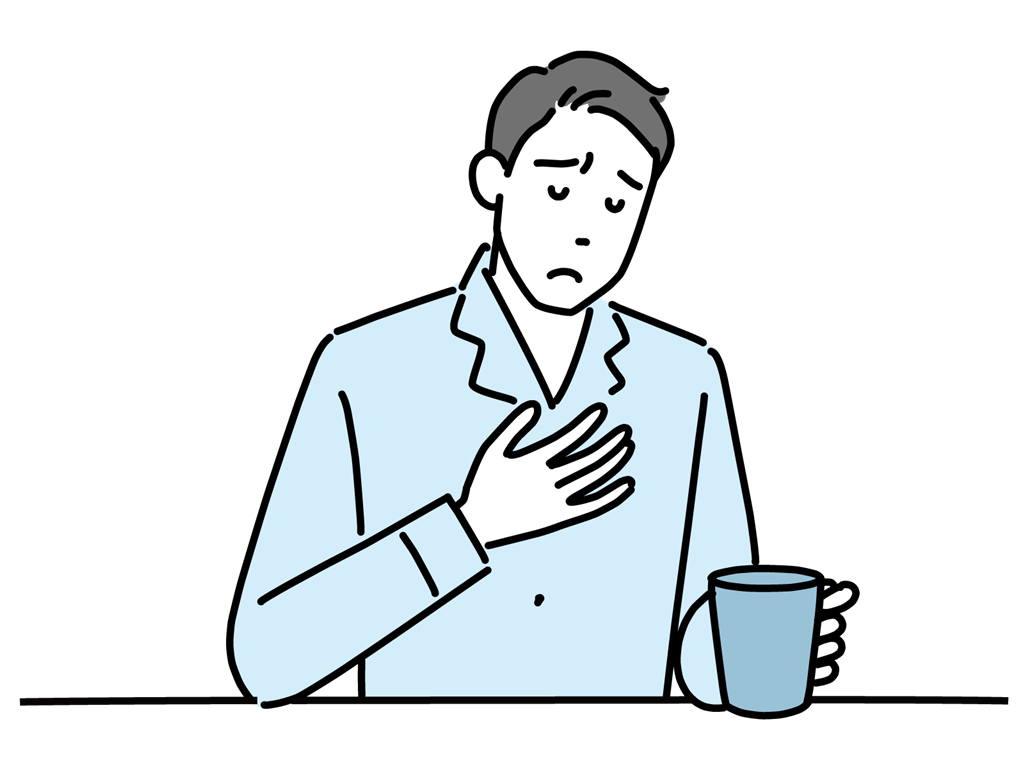
事前審査の段階では団信告知を求めない金融機関が多いのが実情ですが、健康面に不安がある人は、契約前に金融機関へ率直に相談し、団信に加入できるかどうかを早めに確認しておくことが、安心して購入を進めるうえで最も安全な対応策といえるでしょう。
共同買主・連帯保証人の協力を事前確認する
今回の判例では、団信否決の問題だけでなく、共同買主の一人が連帯保証人として融資手続きに協力しなかったことが、最終的にローン不成立と判断される大きな原因となりました。
住宅ローンは単独で借りる場合と異なり、夫婦や親子など複数人で購入する場合には、どちらが主たる債務者になるのか、誰が連帯保証人になるのかといった役割分担を明確にしておく必要があります。
口頭の約束や曖昧な理解のまま契約に進んでしまうと、後になって「保証人にはならない」と拒否され、融資が不成立となり契約自体が履行できなくなるリスクを抱えることになります。
したがって、共同購入を予定している場合は、契約前の早い段階で金融機関や仲介会社を交えて誰が連帯保証人になるのかを確認し、可能であれば書面にして共有しておくことが、トラブル防止のために非常に重要です。
まとめ
住宅ローンは「事前審査=安心」ではありません。本審査では団信告知が行われるだけでなく、物件の担保評価も含めた厳格なチェックが行われます。
東京地裁平成10年5月28日判決が示すように、団信否決だけでなく共同買主が連帯保証人になることを拒んだという事情が重なった結果、ローン特約による解除が認められなかった特殊な事例も存在します。
通常であれば団信否決は融資特約の対象として契約解除が可能なケースが多いものの、買主自身の協力不足や義務違反があると「買主都合」と判断され、大きな不利益を負うリスクがあります。
したがって、同じようなトラブルを避けるためには、まず健康状態に不安がある場合には、できるだけ早い段階で金融機関に相談し、団信に加入できるかどうかを確認しておくことが大切です。
さらに、夫婦や親子など複数人で共同購入する場合は、誰が連帯保証人になるのか、どのような役割分担で融資を受けるのかを事前に明確にし、できれば書面にして合意を残すことが安心につながります。
この二点を徹底することで、契約後に思わぬローン不成立に直面し、手付金放棄などの大きなトラブルに発展するリスクを大幅に減らすことができるでしょう。
本記事は住宅ローン審査や判例の一般的な解説を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言を行うものではありません。個別の案件については必ず弁護士や金融機関等の専門家にご相談ください。
迷ったらプロに相談してみませんか?
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。
小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!





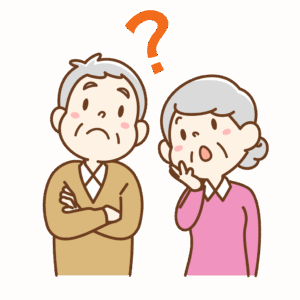



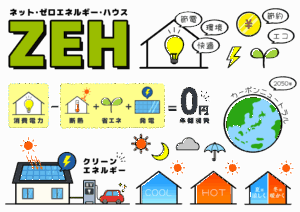


コメント