普通賃貸借契約と定期借家契約の違い|メリット・デメリット・選び方を徹底解説

不動産の賃貸契約には大きく分けて 普通賃貸借契約 と 定期借家契約 の2種類があります。
どちらを選ぶかで、貸主(オーナー)の収益性や将来の活用計画、借主の居住の安定性が大きく変わります。
本記事では、両契約の仕組みを比較するとともに、メリット・デメリットを貸主・借主の立場から整理。さらに「正当事由とは?」「定期借家契約の2パターン」「再契約の仕組みと費用相場」など、実務で必ず押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
普通賃貸借契約とは?
普通賃貸借契約は、日本で最も一般的な賃貸契約方式で、借地借家法により借主の権利が強く保護されている のが特徴です。契約期間は2年程度が多く、満了後も借主が希望すれば更新が可能です。更新料を家賃1か月~1.5か月分程度支払うケースが一般的です。
貸主が契約を終了させるには「正当事由」が必要であり、単なる都合では認められません。

建物の老朽化や建替え、貸主や親族の居住が必要といった社会的に合理性のある事情が求められるため、借主にとっては長期的に安心して住み続けられる契約形態といえます。
定期借家契約とは?
定期借家契約は、平成12年の借地借家法改正によって新たに導入された契約方式で、契約期間が満了すると必ず終了する のが最大の特徴です。通常の普通賃貸借契約と違い、更新の仕組みはなく、引き続き住み続けるには貸主と借主の合意による「再契約」が必要になります。
契約期間は1〜3年程度の短期設定から、5年・10年といった長期設定まで幅広く、貸主の物件活用計画に応じて柔軟に選べます。
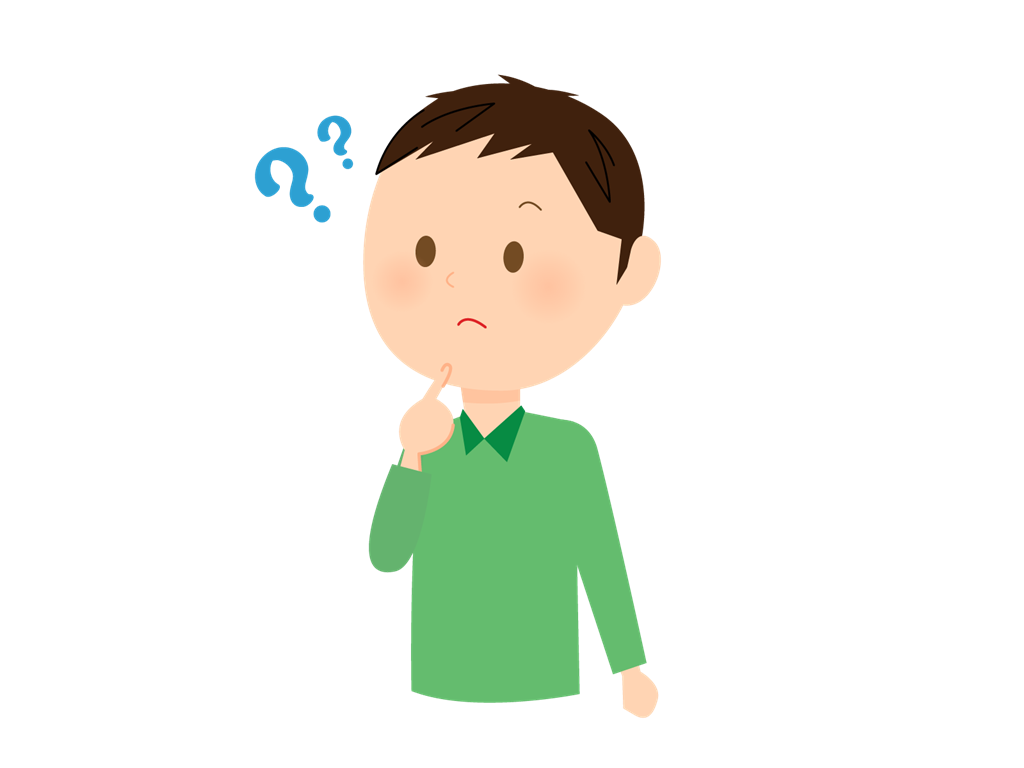
建替えや売却を見据えた一時的な運用や、自宅の建て替えのための仮住まい、自宅売却後次の自宅購入までの自宅として、法人の社宅・単身赴任者向けの短期利用などに適しており、借主よりも貸主の意向を反映しやすい契約形態といえます。
定期借家契約の2パターン
定期借家契約には、大きく分けて 「再契約不可型」と「再契約型」 の2つの方式があります。これは契約期間の長短ではなく、契約満了後に再び契約を結べるかどうか の違いです。
1. 再契約不可型
契約期間が満了すると、その時点で必ず契約が終了するタイプです。更新も再契約も認められず、借主は退去しなければなりません。
この方式は、貸主が将来的に建物を取り壊す予定がある場合や、売却・自己使用を前提としているケースで選ばれることが多いです。借主にとっては居住の継続性がなく、短期的な利用に割り切った契約といえます。
2. 再契約型
一方、再契約型は契約期間満了後に貸主と借主の双方が合意すれば、改めて契約を結び直すことができる タイプです。ここで注意すべき点は、あくまで「自動更新」ではないこと。貸主の同意がなければ再契約は成立せず、借主が希望しても住み続けられる保証はありません。
また、再契約の際には家賃や契約条件が見直されることが一般的で、相場に合わせて賃料が上がるケースや、契約期間が短縮される場合もあります。再契約料は慣習的に 賃料の1か月分程度 とされることが多いですが、地域や物件によって異なるため事前確認が必要です。
普通賃貸借契約のメリット・デメリット
貸主側のメリット
- 長期的に安定した賃料収入を確保できる
- 借主が定着しやすく、空室リスクを抑えられる
- 更新を重ねることで収益が継続しやすい
- 募集・広告コストを削減できる
- 管理会社に委託すれば運用負担が少ない
- 家賃滞納などのトラブルが比較的少ない
- 金融機関評価や融資の安定性が高まる
- 長期収益を前提にした資産運用計画を立てやすい
- 物件価値を維持しやすく、安定経営につながる
- 長期入居者との信頼関係を築きやすい

貸主側のデメリット
- 契約終了には「正当事由」が必要
- 建替え・売却など自由な活用に制約がある
- 家賃を下げても退去を求めにくい
- 借主事情が変わっても対応が難しい
- 立退料の負担が発生する場合が多い
- 更新拒絶には法的ハードルが高い
- 長期入居で建物の劣化が進みやすい
- 家賃の相場調整が難しく収益性が低下することもある
- 売却時に「賃借人付き物件」として評価が下がることがある
- 契約解除をめぐるトラブルで時間と費用がかかる

借主側のメリット
- 更新制度により長期的に住み続けられる
- 家族の生活基盤を安定させやすい
- 将来設計(教育・ローン)が立てやすい
- 更新料を支払えば契約継続が原則保証される
- 借主の居住権が強く保護されている
- 契約終了の不安が少なく安心感がある
- 地域に根付いた生活を続けやすい
- 転勤やライフプラン変更にも柔軟に対応可能
- 長期入居による近隣との関係構築ができる
- 設備改善や修繕を貸主に求めやすい
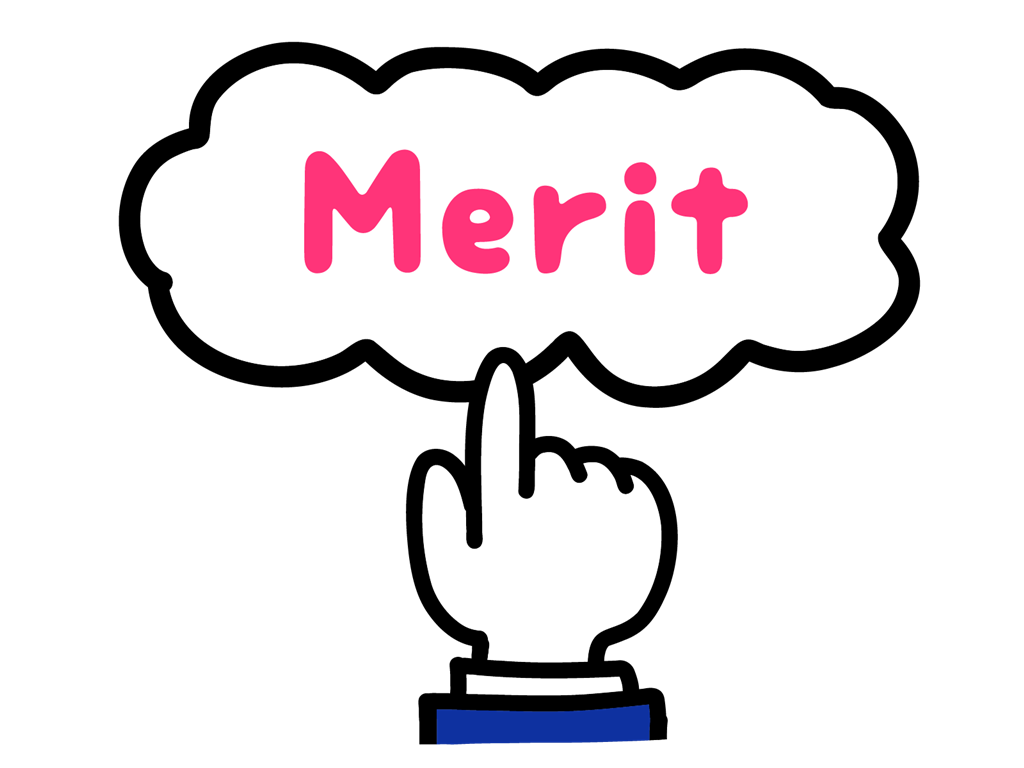
借主側のデメリット
- 更新料が継続的に負担となる
- 貸主都合で更新拒否される場合がある
- 家賃が相場より高止まりしやすい
- 長期居住で設備が古くなっても住み続けざるを得ない
- 契約終了時に立退きを迫られると費用負担が大きい
- 更新時に保証会社や保証人の再審査が必要な場合がある
- 解約予告期間が長く柔軟な住み替えが難しい
- 新築や定期借家より家賃が割高に感じられる場合がある
- 長期居住に伴う共益費・修繕費が増加する可能性
- オーナーとの交渉で不利になるケースもある

定期借家契約のメリット・デメリット
貸主側のメリット
- 契約期間満了で必ず終了できる
- 建替え・売却計画に合わせて柔軟に運用可能
- 短期法人契約・社宅利用に適している
- 高齢者・外国人の入居を受け入れやすい
- 更新を前提としないためトラブルを回避できる
- 自己使用や相続に合わせた利用がしやすい
- 市況に応じて再契約条件を見直せる
- 借主に対して交渉力が高まる
- 賃貸市場の需要変化に対応しやすい
- 不要時に物件を自由に利用できる

貸主側のデメリット
- 借主に敬遠されやすく入居付けが難しい
- 大手法人は定期借家契約を認めないことが多い
- 入居中は売却価格が下がりやすい
- 再契約交渉が必要で収益が安定しにくい
- 契約書面と説明義務が必須で手続きが煩雑
- 長期入居者を確保できない
- 相場より賃料を下げないと借主が見つかりにくい
- 借主の理解不足でトラブルになる可能性
- 募集に時間がかかり空室期間が長くなる場合がある
- 借主から敬遠されることで競争力が低下する

借主側のメリット
- 契約期間が明確で短期居住に便利
- 家賃が相場より安くなるケースが多い
- ライフスタイルに合わせて柔軟に選べる
- 再契約で一定期間延長できる可能性がある
- 転勤・留学・単身赴任など期間限定利用に最適
- 更新料が発生しない
- 契約終了が事前に分かるため住み替え準備ができる
- 短期で複数物件を試し住みできる
- 家賃交渉で有利になるケースがある
- 契約内容を比較的自由に調整しやすい
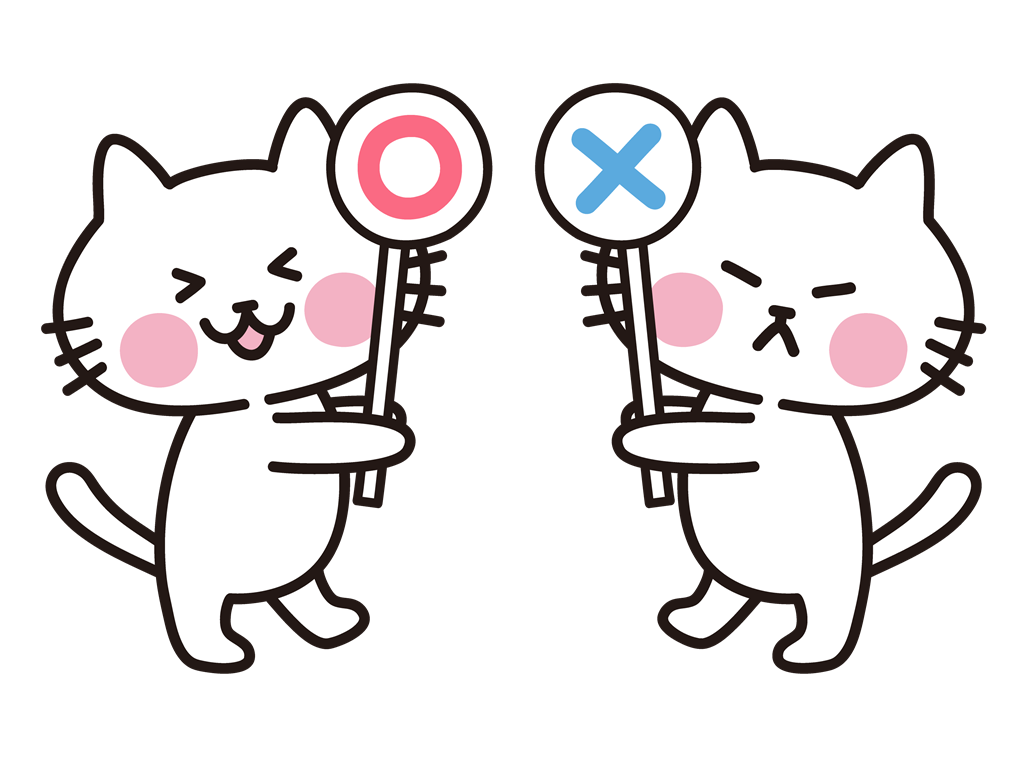
借主側のデメリット
- 契約満了で必ず退去しなければならない
- 再契約は貸主の意向に左右される
- 長期居住には不向き
- 引越し費用が定期的に発生するリスク
- 安定した生活基盤を築きにくい
- 子育てや教育環境の継続が難しい場合がある
- 再契約料が新たに発生(家賃1か月分程度)
- 将来の住居計画が不確実で精神的負担になる
- 賃貸ローン審査や学校の転入届に不安が出る場合がある
- 定期借家を理解していない保証人との間でトラブルになる可能性

正当事由とは?
普通賃貸借契約では、貸主が更新を拒否するには「正当事由」が必要です。
これは単に「貸主が住みたい」という一方的な理由だけでは足りず、借主の居住利益と比較衡量 されて判断されます。
主な正当事由の例
- 貸主または親族がその物件に居住する必要がある
- 建物の老朽化や建替えの必要性
- 長期にわたる家賃滞納や重大な契約違反
- 物件を売却し、貸主がその収益を生活資金に充てる必要がある
裁判例では、単なる貸主の希望だけでは認められず、立退き料の支払い など借主への補償がセットで求められるケースが多いです。つまり、貸主にとってはハードルが高く、借主保護が優先される仕組みになっています。
再契約について
定期借家契約は更新制度がなく、契約期間が満了すると必ず終了する仕組みになっています。借主がどれほど住み続けたいと希望しても、自動的な延長は認められません。ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、新たに条件を取り決めて「再契約」を結ぶことができます。再契約はあくまで新規契約に近い扱いとなるため、家賃や契約内容が見直されることもあり、必ずしも同じ条件で住み続けられるとは限りません。
再契約の特徴
- 新規契約と同様に、条件を改めて取り決める必要がある
- 賃料の見直しが行われることがある(相場や物件状況を反映)
- 再契約料は 賃料の1ヶ月分程度 が一般的な相場
- 再契約が前提ではないため、確実に住み続けられる保証はない
借主としては「必ず再契約できる」とは考えず、あくまで貸主の意向次第である点に注意が必要です。
どちらを選ぶべきか?ケース別判断ポイント
オーナーの場合
- 長期安定収益を得たい → 普通賃貸借契約
- 将来の建替え・売却を予定している → 定期借家契約
- 短期法人契約・社宅需要に対応したい → 定期借家契約
- 空室リスクを最小化したい → 普通賃貸借契約
- 高齢者・外国人入居にも柔軟に対応したい → 定期借家契約
- 金融機関からの融資評価を重視する → 普通賃貸借契約(長期安定収入がプラス評価になる)
- 将来自分や家族が住む可能性がある → 定期借家契約(終了を確実にできるため)
- 市場の賃料相場に合わせて柔軟に調整したい → 定期借家契約(再契約時に条件を見直せる)
- 募集コストや管理コストを抑えたい → 普通賃貸借契約(長期入居者を確保できる)
- リスク分散や自由度を優先したい → 定期借家契約(将来の方針変更に合わせやすい)
借主の場合
- 長期的に腰を据えて住みたい → 普通賃貸借契約
- 転勤・進学など将来が不確定 → 定期借家契約も選択肢
- 家賃をできるだけ抑えたい → 定期借家契約
- 更新料負担を避けたい → 定期借家契約
- 安定的な生活基盤を求める → 普通賃貸借契約
- 子育てや教育環境を継続したい → 普通賃貸借契約(途中退去の心配が少ない)
- 短期間だけの居住を予定している(単身赴任・留学など) → 定期借家契約
- 契約終了が決まっていたほうが次の住まい計画を立てやすい → 定期借家契約
- 地域に根差した人間関係や生活環境を築きたい → 普通賃貸借契約
- 市場相場より安めの賃料を重視したい → 定期借家契約
まとめ
普通賃貸借契約と定期借家契約は、それぞれに明確な特徴とメリット・デメリットがあります。
- 普通賃貸借契約 は借主保護が強く、安定的に住み続けたい人や長期収益を狙うオーナーに適しています。ただし、貸主側にとっては契約終了のハードルが高く、建替え・売却の自由度が制約される点に注意が必要です。
- 定期借家契約 は契約満了で終了するため、貸主にとって将来の計画を立てやすい契約方式です。短期利用や特殊なニーズに対応できる一方、借主から敬遠されやすく、入居付けの際には家賃を相場より下げる必要が出ることもあります。
結論として、どちらを選ぶべきかは 物件の特性・オーナーの運用方針・借主のライフプラン によって異なります。契約前に両者の違いを正しく理解し、想定される将来の変化に備えた契約形態を選ぶことが、後悔しない不動産運用・居住の第一歩となるでしょう。
迷ったらプロに相談してみませんか?
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。
小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!




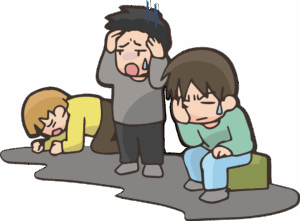





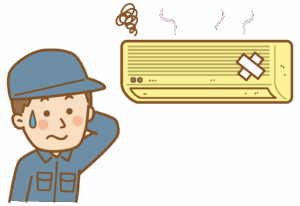
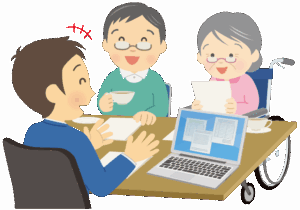
コメント