法定相続割合と遺留分の完全ガイド|相続トラブルを防ぐための基礎知識
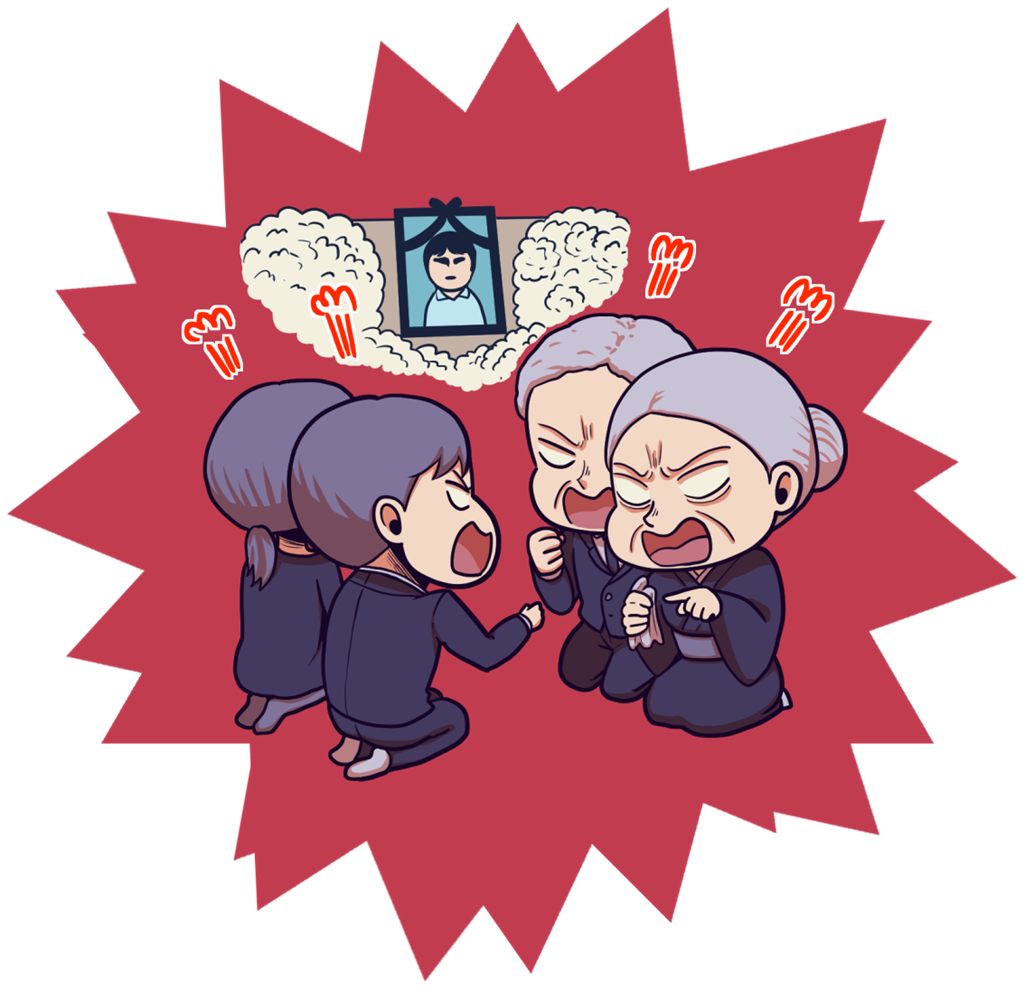
相続が発生すると、遺産をどう分けるかが大きな課題となります。
遺言書があればその内容に従うのが原則ですが、遺言がない場合には「法定相続割合」が基準となります。
また、たとえ遺言で偏った分け方が指定されていたとしても、配偶者や子ども、直系尊属には「遺留分」という最低限の取り分が保障されており、完全に排除することはできません。
実際の相続トラブルの多くは、この法定相続割合や遺留分を正しく理解していないことから発生します。
本記事では、民法に基づいた相続割合と遺留分の仕組みを詳しく解説し、実務で注意すべきポイントを整理します。
法定相続割合の基本
法定相続割合とは何か
法定相続割合とは、民法第900条に規定されている「相続人ごとの取り分の割合」です。遺言がなければこの割合に従って遺産を分けるのが原則となります。例えば配偶者と子どもが相続人であれば、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を均等に分ける、という具合です。
ただし、これはあくまでも「基準値」にすぎません。実際の遺産分割では、遺産の内容(不動産や預貯金など)や相続人の生活状況を踏まえ、話し合いで法定割合と異なる分け方をすることも可能です。

しかし協議がまとまらない場合や、調停・審判に発展した場合には、この法定相続割合が裁判所の判断の基準として機能します。したがって、相続に直面した際には「まず法定相続割合を正しく理解すること」が出発点となります。
配偶者の取り分は必ず存在する
相続において特徴的なのは、配偶者が常に相続人となる点です。配偶者の取り分は、子どもや親、兄弟姉妹といった他の相続人の有無によって変動します。
例えば、配偶者と子どもが相続する場合には配偶者が2分の1、配偶者と両親が相続する場合には配偶者が3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者が4分の3を取得します。配偶者の生活を守る観点から、他の相続人よりも手厚く取り分が保障されているのです。
一方で注意すべき点として、法律婚をしていない内縁関係のパートナーには相続権がありません。長年連れ添っていたとしても、遺言で指定しなければ財産を受け取れないのです。熟年再婚や事実婚が増えている現代では、こうしたケースで深刻なトラブルになることも珍しくありません。配偶者の権利は強い一方、法律婚であることが前提になる点を理解しておきましょう。
代表的な相続割合のパターン
相続人の組み合わせごとに法定相続割合は異なります。代表的な例を整理すると次の通りです。
- 配偶者+子ども → 配偶者1/2、子ども全員で1/2
- 配偶者+両親 → 配偶者2/3、両親で1/3
- 配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4
- 配偶者なし → 子どものみなら全額を均等、両親のみなら全額を均等、兄弟姉妹のみなら全額を均等(ただし異母兄弟は半分)
不動産など分割しにくい財産の場合、法定割合どおりに分けるのは難しいため、売却して現金化する「換価分割」や、特定の相続人が取得して代償金を支払う「代償分割」が行われることが多いです。特に不動産を含む遺産では、法定割合がそのまま実務に落とし込めないため、柔軟な工夫が必要となります。
遺留分の基本知識
遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人が遺言や生前贈与によって財産の分け方を自由に決められるとしても、一定の相続人に保障される「最低限の取り分」を意味します。
例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の子どもや配偶者は遺留分を請求することが可能です。遺留分は相続人の生活基盤を守るとともに、著しい不公平を防ぐために設けられています。

また、遺留分の算定にあたっては相続税評価額ではなく、不動産や株式などの実勢価格(時価ベース)をもとに評価される点にも注意が必要です。そのため、相続税の計算とは異なり、実際の市場価値を踏まえて取り分が決まるケースが多くなります。
相続トラブルの多くは「遺言によって取り分が極端に偏った」ケースで発生するため、この遺留分の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。
遺留分を持つ人・持たない人
遺留分が認められるのは、配偶者・子ども・直系尊属(両親や祖父母)です。これらの人々は、生活を共にしたり扶養関係にあったりすることから、最低限の取り分が保障されています。
一方で兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって「全財産を配偶者に相続させる」という遺言があった場合でも、兄弟姉妹が異議を唱えることはできません。この点を誤解しているケースは意外に多く、「兄弟なのに遺留分を請求できないのか」と驚かれることもあります。遺留分の有無は相続人の種類によって大きく異なるため、しっかり整理しておくことが必要です。
遺留分の割合
遺留分は法定相続分のさらに一定割合として決まっています。
- 配偶者や子どもが相続人 → 法定相続分の1/2
- 直系尊属のみが相続人 → 法定相続分の1/3
例えば、財産が6000万円、配偶者と子ども2人が相続人という場合、法定相続分は配偶者1/2(3000万円)、子ども全員で1/2(3000万円)です。遺留分はそれぞれの半分となるため、配偶者1500万円、子どもは1人あたり750万円となります。
このように遺留分は「完全にゼロにはできないが、法定相続分より少ない」という性質を持っています。遺言でどのように指定しても、このラインを下回ると争いの原因になるのです。
遺留分の計算方法
算定基礎財産の考え方
遺留分を計算する際の基準となるのが「遺留分算定基礎財産」です。これは相続開始時の財産額に、相続開始前1年間に行われた贈与を加算し、さらに債務を差し引いた額です。
重要なのは「生前贈与が考慮される」という点です。例えば被相続人が亡くなる直前に特定の子どもへ多額の資金援助をしていた場合、それも含めて遺留分を計算します。ただし日常生活費や社会通念上相当とされる贈与は対象外となるため、どこまでを加算するかは争点になりやすいです。
また、借金があればそれを差し引くため、債務の多い遺産では遺留分も小さくなる場合があります。単純に「財産の金額」だけでなく、負債や過去の贈与を含めて全体像を把握することが欠かせません。
具体的な計算例
例1:財産5000万円、借金1000万円、配偶者と子ども2人が相続人の場合
基礎財産=5000万-1000万=4000万
法定相続分=配偶者2000万、子ども2000万(各1000万)
遺留分=その半分 → 配偶者1000万、子ども各500万
例2:財産8000万円、親のみが相続人の場合
基礎財産=8000万
法定相続分=親2人で4000万ずつ
遺留分=法定相続分の1/3 → 親2人で各約1333万
このように、同じ財産額でも相続人の種類によって遺留分は大きく変わります。実務では複雑なケースが多く、専門家による試算が欠かせません。
遺留分侵害額請求の実務
請求の手続きと流れ
遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使できます。以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、改正民法で名称と性質が変わり、金銭債権として請求する形になりました。
手続きはまず他の相続人に内容証明郵便で通知し、協議を行います。協議でまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決できなければ裁判に進む流れです。

期限は「相続開始と侵害を知ったときから1年以内」、または「相続開始から10年以内」と定められており、これを過ぎると請求権が消滅します。
実務では期限を知らずに権利を失うケースもあり、早期の対応が重要です。
金銭請求が原則であること
遺留分侵害額請求は、原則として「金銭」で支払われます。不動産を直接分け与える必要はなく、受け取った相続人が現金で清算すれば足ります。これは不動産の権利関係を複雑化させないための制度です。
ただし、不動産が遺産の大半を占める場合には、現金で支払うのが難しいこともあります。その場合には、不動産の共有持分を譲渡する形で実質的に調整するケースもあり、柔軟な対応が求められます。実務では「不動産の評価額」をどう算定するかが争点となり、鑑定士の評価を依頼する場面も少なくありません。
法定相続割合と遺留分の違い
似て非なる二つの概念
法定相続割合と遺留分は混同されやすいですが、全く異なる性質を持っています。
- 法定相続割合:遺言がない場合の基本的な分け方の基準
- 遺留分:遺言や贈与があっても最低限保障される取り分
つまり、法定相続割合は「スタートライン」、遺留分は「最低限守られるゴールライン」と言えます。実際の相続では、遺言や協議によって法定割合から外れることも多いですが、その場合でも遺留分を下回ると争いが生じるのです。
たとえば「全財産を配偶者に相続させる」という遺言は有効ですが、子どもは遺留分を請求することで一定の金銭を受け取ることができます。この違いを理解していないと、「遺言だから絶対」と誤解し、後々トラブルに発展しかねません。
注意点と対策
不動産が中心の遺産分割の難しさ
日本の相続では、不動産が財産の大部分を占めるケースが多いです。その場合、法定相続割合や遺留分をそのまま現物で分けるのは困難です。
例えば「土地を2分の1ずつに分ける」といっても、現実には分筆や利用価値の差があり、均等にはなりません。
結果として「売却して現金化」か「特定の相続人が取得して代償金を払う」方法をとることになります。どちらにしても相続人全員の合意が必要であり、感情的な対立が激化すると解決まで長期間を要することになります。

相続税との関係
法定相続割合や遺留分は、相続税の計算とも密接に関係します。
特に配偶者には「配偶者控除」があり、1億6000万円または法定相続分相当額までは非課税となります。これを活用するかどうかで税額は大きく変わります。
また、遺留分を侵害していた場合に後から金銭を支払うと、その支払い額は相続税の課税対象となる可能性があります。相続割合の調整と税務処理は切り離せないため、税理士の関与が不可欠です。
トラブルを避けるための生前対策
相続トラブルを防ぐためには、生前からの準備が重要です。具体的には次のような対策が効果的です。
- 公正証書遺言を作成して意思を明確にしておく
- 生前贈与や生命保険を活用して分割をしやすくする
- 家族間で事前に話し合い、情報を共有しておく
こうした対策を講じることで、法定相続割合や遺留分をめぐる争いを最小限に抑えることができます。

まとめ
相続において法定相続割合は「基準」、遺留分は「最低限保障された取り分」という異なる役割を持ちます。両者を正しく理解していないと、遺産分割協議が長引いたり、裁判に発展したりするリスクが高まります。特に不動産や生前贈与が絡む場合には、実務上の判断が複雑になりやすいため、専門家への相談が不可欠です。
相続は「争族」とも言われるように、感情的な対立を生みやすい場面です。法定相続割合と遺留分の知識を押さえ、早めに準備を進めることが、家族の負担を減らし円満な解決につながる第一歩となります。
不動産売却・賃貸募集・賃貸管理のお悩みはプロに無料相談!
不動産会社セレクトビジョンにお任せください!
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!




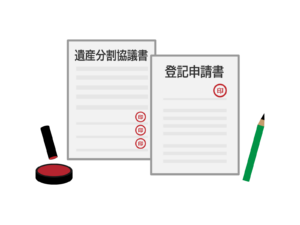


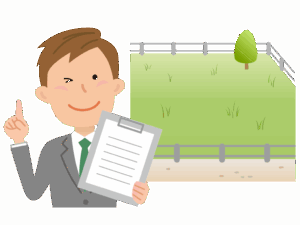


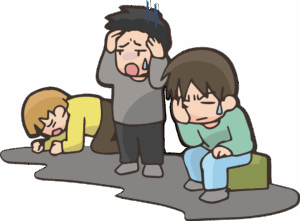

コメント