不動産投資の減価償却と税金の先送り|売却で失敗しないための完全ガイド

不動産投資を始めると、多くの人が「減価償却を使えば節税できる」と耳にします。確かに帳簿上の利益を抑えれば所得税や住民税を軽減でき、給与所得と損益通算することで還付を受けられることもあります。しかし実際には「税金を消している」のではなく、将来の課税を先送りしているだけです。
さらに、不動産業者に確定申告を任せてしまい、建物割合を大きめに設定して減価償却を突っ込みすぎると、売却時に大きな課税が発生する「税金爆弾」を抱えることになります。
本記事では、不動産投資における減価償却の仕組みや耐用年数の基礎知識、実例シミュレーション、そして業者任せにした場合のリスクと出口戦略を、事例を交えながら徹底解説します。
不動産投資における減価償却とは?
減価償却の基本的な仕組み
不動産は土地と建物に分けられますが、土地は劣化しないため減価償却できません。建物や設備は時間とともに劣化する資産とみなされ、耐用年数に基づいて少しずつ経費として計上します。これが「減価償却」です。
例えば、建物価格1,200万円・耐用年数47年(RC造)のマンションを購入した場合、毎年およそ26万円を経費化できます。これにより課税所得を減らし、税負担を軽くすることができます。

減価償却のメリットと投資家に与える効果
- 所得税・住民税の軽減につながる
- 損益通算で給与所得からの税還付を受けられる場合がある
- キャッシュフローが改善し、再投資や繰上げ返済に回せる
減価償却を活用すると、特に投資初期に資金繰りが楽になるのは確かです。ただし「メリットの裏には必ず将来の課税負担がある」という前提を忘れてはいけません。
減価償却と耐用年数の基礎知識
建物構造ごとの耐用年数
建物の耐用年数は、構造によって大きく異なります。
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 軽量鉄骨造(厚3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨造(3mm超4mm以下) | 27年 |
| 軽量鉄骨造(4mm超) | 34年 |
| RC・SRC造 | 47年 |
耐用年数が長いほど、減価償却のスピードは遅くなり、毎年の経費化額は少なくなります。逆に木造や軽量鉄骨は早く償却できるため、初期の節税効果は大きいですが、その分売却時の簿価は急速に小さくなります。
中古物件の残存耐用年数の計算方法
中古不動産は「残存耐用年数」を計算し直して償却します。
計算式は以下の通りです。
残存耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%(最低2年)
例:築30年のRC(耐用年数47年)の場合
(47 − 30) + 30×20% = 17+6 = 23年
つまり、新築なら47年で償却する建物も、中古であれば23年で減価償却できることになります。
設備・内装の耐用年数と償却スピード
建物本体とは別に、設備や内装も耐用年数が定められています。
設備は短期で償却できるため、購入時にリフォームや設備投資を行えば、当初の減価償却費を増やして経費化することも可能です。
| 区分 | 耐用年数 | 具体例 |
|---|---|---|
| 給排水・衛生設備 | 15年 | 給湯設備、浴槽、洗面台、トイレなど |
| 電気設備(一般) | 15年 | 照明設備、配線、分電盤など |
| 電気設備(冷暖房用) | 6年 | エアコン、ガスヒーター、電気ストーブなど |
| ガス設備 | 15年 | ガス配管、ガス給湯器、ガスコンロ等 |
| エレベーター設備 | 17年 | 乗用エレベーター |
| 消火・防災設備 | 15年 | 消火栓、スプリンクラー、非常放送装置等 |
| 内装仕上げ(木造・軽量鉄骨造) | 15年 | クロス、フローリング、天井仕上げ、間仕切り等 |
| 内装仕上げ(RC造) | 15年 | 同上 |
ポイント
- 建物本体よりも短い耐用年数が多く、経費化を早められる。
- 特にエアコンや給湯器は6年と短いため、買い替えや修繕の際に一度に償却できる。
- 内装リフォームをした場合も「15年」で償却するのが基本。

減価償却は「節税」ではなく「税金の先送り」
税金が繰り延べされる仕組み
減価償却を行えば、確かに毎年の課税所得を減らすことができ、当初の税負担を軽減する効果があります。しかしその一方で、減価償却を計上すればするほど帳簿上の資産価額(簿価)は年々小さくなっていきます。
やがて売却のタイミングを迎えたとき、実際の売却価格と簿価との差額が「譲渡益」として一括で課税対象となります。つまり、毎年の税金を抑えているのは「消えた税金」ではなく、あくまで将来に支払いを繰り延べている状態にすぎないのです。
短期的にはキャッシュフローが良く見えても、出口でまとめて課税されるリスクを理解していなければ、資金計画が大きく狂う可能性がある点に注意が必要です。
実例シミュレーションで見る税金ショック
ケース①:購入価格2,000万円
- 購入価格:2,000万円(建物1,200万/土地800万)
- 10年で建物を1,000万償却 → 簿価は土地800万+建物200万=1,000万
- 売却価格:1,800万円
- 譲渡益 = 1,800万 − 1,000万 = 800万
- 長期譲渡(5年超)税率20% → 160万円の税金
ケース②:購入価格3,500万円
- 購入価格:3,500万円(建物2,100万/土地1,400万)
- 10年で建物を1,800万償却 → 簿価は土地1,400万+建物300万=1,700万
- 売却価格:3,000万円
- 譲渡益 = 3,000万 − 1,700万 = 1,300万
- 長期譲渡(5年超)税率20% → 260万円の税金
ケース③:購入価格5,000万円
- 購入価格:5,000万円(建物3,000万/土地2,000万)
- 10年で建物を2,500万償却 → 簿価は土地2,000万+建物500万=2,500万
- 売却価格:4,200万円
- 譲渡益 = 4,200万 − 2,500万 = 1,700万
- 長期譲渡(5年超)税率20% → 340万円の税金
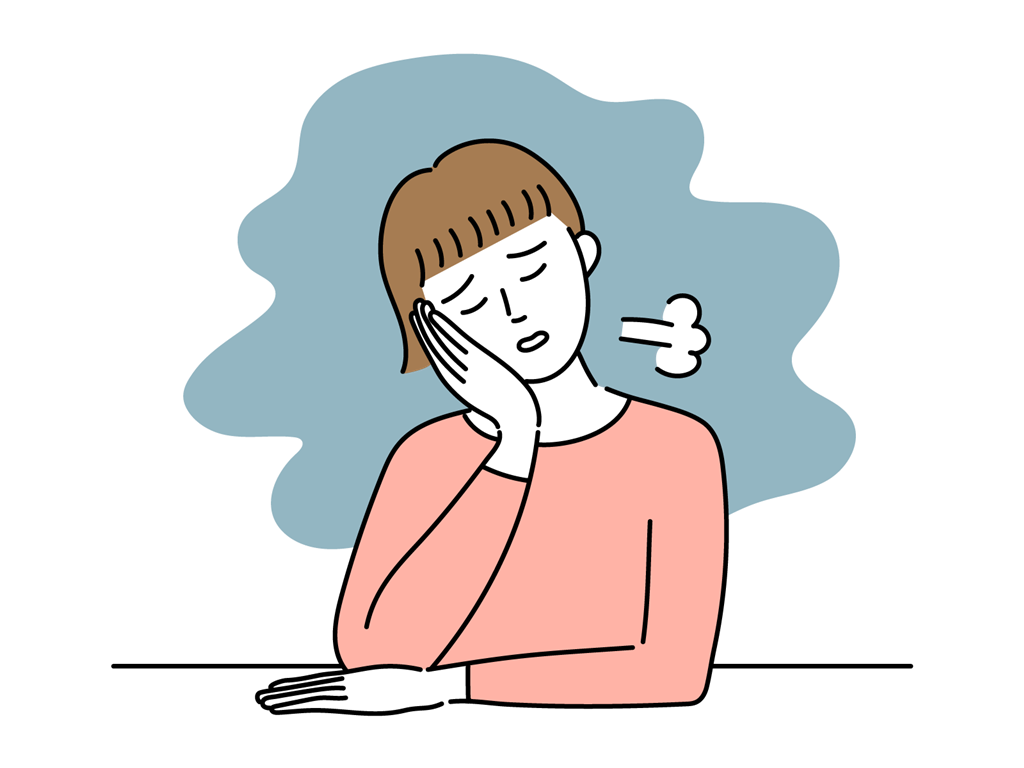
➡ 減価償却をしなければ譲渡益はもっと小さく済んだはずが、帳簿価額が下がったために課税額が大きくなっています。
売却時の短期譲渡・長期譲渡の課税率
- 短期譲渡(5年以下保有):約39%課税(所得税30%+住民税9%)
- 長期譲渡(5年超保有):約20%課税(所得税15%+住民税5%)
減価償却を進めるほど売却時の譲渡益が膨らみ、結果的に重い税負担となります。
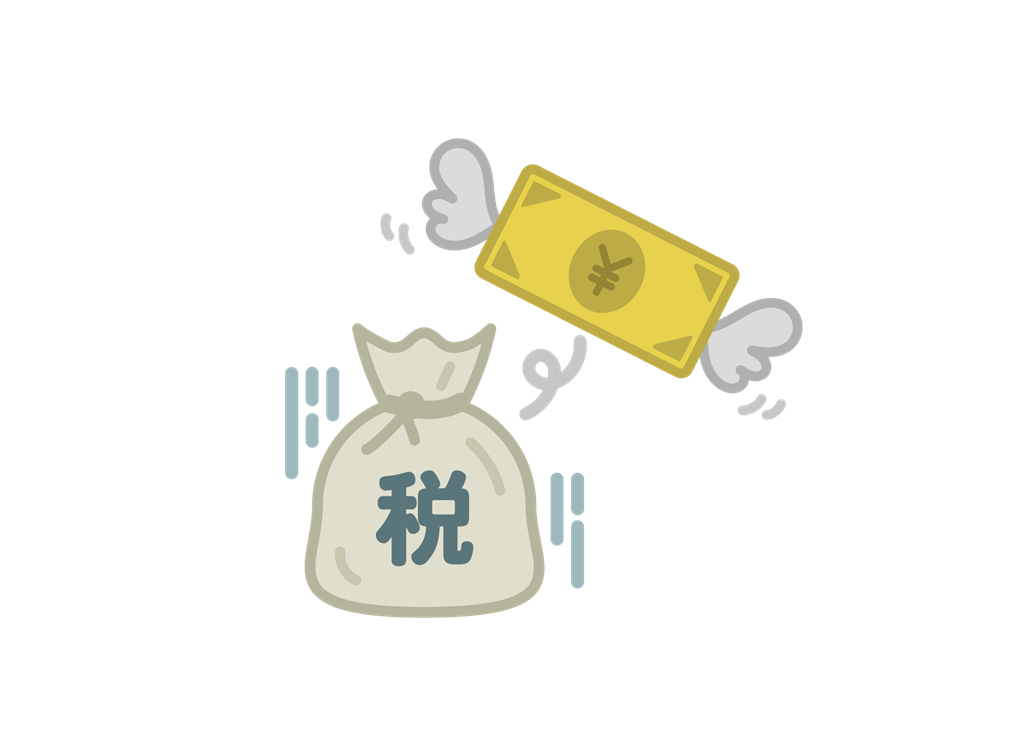
不動産業者に確定申告を任せた場合のリスク
建物割合を大きく設定されるケース
一部の不動産業者は「節税効果を最大化できます」と強調し、購入時の建物と土地の割合を実態以上に建物寄りに設定して確定申告させることがあります。通常であれば建物60%・土地40%程度が妥当なケースでも、建物80%といった極端な配分にしてしまうのです。
建物部分が大きければ大きいほど減価償却費を多く計上でき、当初は見かけ上の節税効果が高まります。しかし実際には帳簿上の建物価額が急速に減っていくため、売却時には簿価との差額が大きく膨らみ、想定以上の譲渡所得税が課されるリスクを抱えることになります。
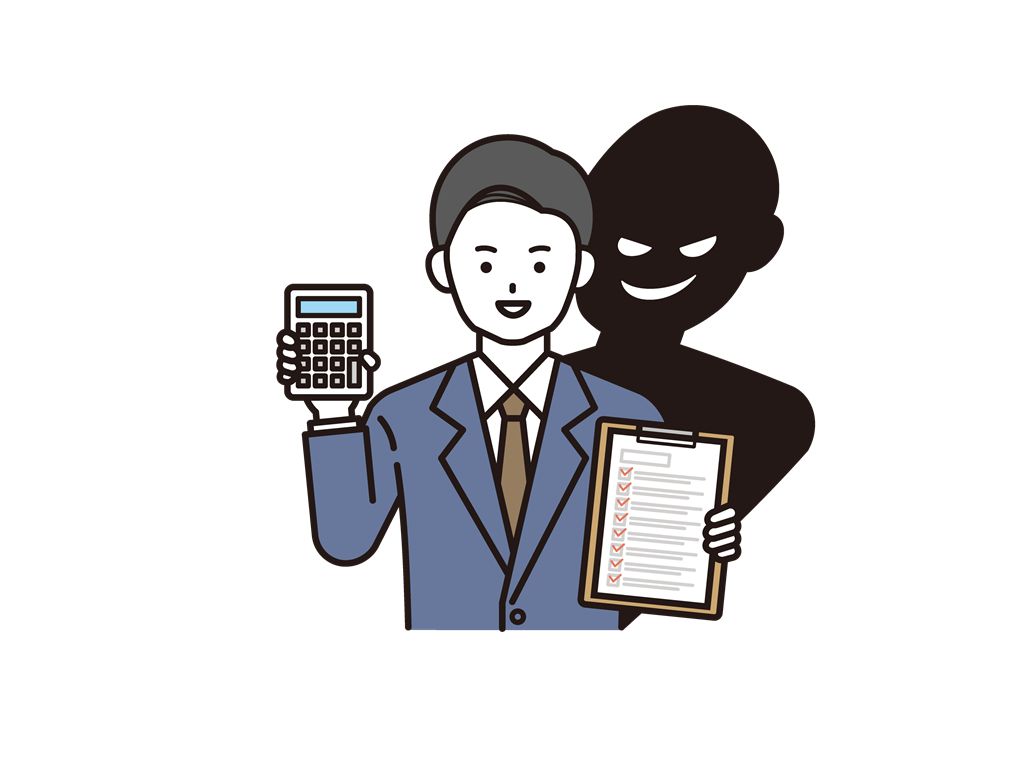
過度な減価償却で起きる売却時の悲劇
当初は減価償却を大きく計上することで所得税や住民税が軽減され、「節税ができて投資効果が高い」と感じられるかもしれません。しかし、その裏側では帳簿上の建物価額が急速に減少していきます。結果として売却のタイミングを迎えると簿価が極端に低くなり、実際の売却価格との差額、つまり譲渡益が大きく跳ね上がることになります。その結果、本来であれば数十万円程度で済むはずだった納税額が、数百万円単位に膨らむことも珍しくありません。さらに想定外の納税資金を用意しなければならず、ローン返済や次の投資計画に充てるはずだったキャッシュフローが一気に悪化し、資金繰りに深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
税理士法違反リスクと税務否認の可能性
確定申告は税理士の独占業務です。不動産会社が無資格で代行することは税理士法違反の可能性があります。また、建物割合を不自然に高く設定すれば、税務調査で否認され、追徴課税を受けるリスクも高まります。
不動産投資で失敗しやすい典型パターン
- 減価償却=節税と誤解している
- 出口課税を考えずに購入している
- 不動産業者に確定申告を丸投げしている
- 高値掴みした割高物件でスタートしている
- 毎年の赤字申告で銀行評価が下がり、次の融資が受けにくくなる

不動産投資で成功するための出口戦略
長期保有でインカムゲインを積み上げる
不動産投資の本質は、短期的な節税効果や売却益を狙うことではなく、「インカムゲイン=家賃収入」を安定的に確保することにあります。毎月の家賃収入からローン返済や維持費を賄いながら着実に借入残高を減らし、長期的に保有していくことで資産は徐々に純資産へと変わっていきます。最終的にローンを完済すれば、返済負担のない純粋な家賃収入が手元に残るようになり、これが不動産投資における最大の強みとなります。安定したキャッシュフローは老後資金や生活基盤の柱となり、さらには次世代への資産承継にもつながるため、長期保有を前提としたインカム重視の姿勢こそが不動産投資の王道だといえるのです。
売却を補助的な選択肢として考える
市況が良く不動産価格が高騰しているタイミングや、都心や駅近など資産価値が落ちにくい立地であれば、売却益(キャピタルゲイン)を狙うのも有効な戦略のひとつです。実際にうまくタイミングをとらえれば大きな利益を確保できる可能性もあります。しかし、こうした値上がり益は景気や金融政策、需給バランスなど外部要因に大きく左右されるため、常に再現性があるとは限りません。むしろ短期的な値動きに依存する投資スタイルはリスクが高く、計画どおりにいかないケースが多いのが実情です。そのため、不動産投資の基本はあくまで長期保有で家賃収入を積み上げる「インカムゲイン重視」の姿勢に置き、売却益の追求は補助的な手段として位置付ける方が安全かつ堅実な戦略といえるでしょう。
相続・法人化を活用した税務戦略
- 相続:不動産を相続する場合、相続時点の時価で資産評価が行われるため、それまでに計上してきた減価償却の影響がリセットされるケースがあります。つまり、被相続人が長年にわたって減価償却を積み重ねて簿価が大きく下がっていても、相続人は取得時点の時価を新たな基準にして資産を引き継げるため、売却時の譲渡益を小さく抑えられる可能性があります。これは、長期保有を前提にした不動産投資において「相続」という出口戦略を選択する大きなメリットのひとつです。特に、次世代に資産を承継したいと考える投資家にとっては、税負担を最小化しながら資産価値を守る有効な手段となります。
- 法人化:不動産投資を法人化すると、課税が法人税ベースで行われるようになります。日本の法人税率は中小企業の場合おおよそ23%前後で推移しており、所得税の累進課税(最大55%)と比べて大きく抑えられるケースがあります。特に不動産収入が高額になり個人の課税負担が重くなる場合、法人を設立して物件を保有すれば、節税効果に加えて経費計上の自由度が高まるという利点も得られます。さらに、法人名義にすることで金融機関からの融資が受けやすくなり、規模拡大を目指す投資家にとっても有利に働く可能性があります。
【事例比較】失敗する投資家と成功する投資家の違い
業者任せで確定申告した失敗事例
ある投資家は、不動産会社の提案どおり建物割合を80%に設定し、過度に減価償却を行いました。確定申告も業者が代行。購入から10年後、1,800万円で売却したところ簿価が1,000万円しか残っておらず、譲渡益800万円が発生。結果として160万円以上の税金が発生し、当初の「節税効果」が帳消しになりました。
税理士と相談して戦略的に運用した成功事例
別の投資家は、建物割合を適正に設定し、税理士と相談して確定申告を行いました。減価償却は適度に活用しつつ、売却ではなく長期保有を前提にインカムゲインを重視。最終的にローンを完済し、相続を見据えて資産を承継したため、課税リスクを最小化できました。
まとめ|減価償却を正しく理解して不動産投資を成功させる
不動産投資における減価償却は「節税」ではなく「課税の先送り」です。不動産業者に申告を任せて過度に償却すると、売却時に税金爆弾を抱えることになります。
✅ 成功のポイント
- 耐用年数に基づき正しく減価償却する
- 確定申告は税理士に相談し、業者任せにしない
- 投資の基本は長期保有のインカムゲイン、売却や相続は補助的に活用
この3点を押さえることで、将来の税金ショックを避け、安定的な不動産投資を実現することができます。
賃貸募集・賃貸管理のお悩みはプロに無料相談!
東京都新宿区高田馬場|不動産会社セレクトビジョンにお任せください!
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。
小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!




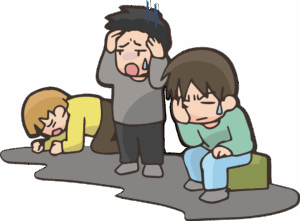





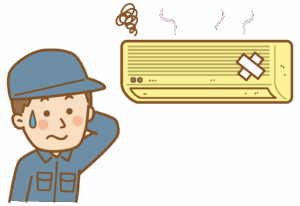
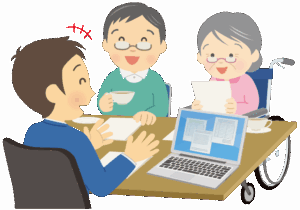
コメント