相続税評価を下げる特例|自宅・賃貸土地・建物の扱いと注意点

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産をもとに相続税が計算されます。特に不動産は評価額が大きくなりやすく、課税額を大きく左右するため、多くの家庭で悩みのタネとなります。
しかし、国は「自宅を相続して住み続ける」「賃貸物件をそのまま引き継ぐ」といった場合に、相続税の計算上の評価額を大きく下げられる特例を設けています。これにより、課税対象となる評価額を数千万円単位で減らせるケースもあります。
本記事では、
- 自宅に使える 小規模宅地等の特例(最大80%減額)
- 賃貸用土地に使える 小規模宅地等の特例(最大50%減額)
- 建物の評価方法と位置づけ
- 区分マンション1室を賃貸している場合の扱い
- 数値例とシミュレーション
をわかりやすく解説します。
① ✅ 自宅は「小規模宅地等の特例」で最大80%減額(330㎡まで)
制度の概要
被相続人が実際に住んでいた自宅の土地については、相続人が引き続き生活の拠点として利用するなど一定の条件を満たせば、相続税評価額を大幅に引き下げることができます。
具体的には、小規模宅地等の特例を活用することで、最大で評価額の80%を減額することが可能です。
たとえば1億円の評価額が2,000万円まで圧縮されるため、課税の基礎となる金額を大幅に減らせる点で非常に有効です。

なお、この特例の対象となる土地には上限があり、330㎡までの部分が減額の適用範囲となります。都市部の戸建て住宅であればほとんどの場合はこの面積内に収まりますが、郊外や地方で広い土地を所有している場合には、一部のみが特例の対象となり、それを超える部分については通常の評価が適用されます。
適用条件
- 配偶者が相続する場合(無条件で適用可能)
- 同居していた子が相続する場合
- 同居していなくても、相続人本人や配偶者が自宅を所有していない場合
数値例(評価額ベース)
自宅の土地評価額が 1億円(300㎡) の場合:
- 特例なし → 評価額1億円
- 特例あり → 評価額2,000万円(▲8,000万円)
👉 相続税の課税対象となる評価額が 8,000万円下がる。
実際の相続税額の減少幅は、相続人の人数や税率区分によって異なります。
② ✅ 賃貸用の土地は「小規模宅地等の特例」で最大50%減額(200㎡まで)
制度の概要
被相続人が生前にアパートや賃貸マンションを所有し、賃貸事業として貸していた土地については、相続税評価額を軽減できる制度が用意されています。
具体的には、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の対象となり、一定の要件を満たすことで評価額を半分に引き下げることが可能です。
適用面積の上限は200㎡までで、その範囲内の土地に対して50%の減額が認められます。

たとえば、相続税評価額が4,000万円の賃貸用地であれば、特例を使うことで評価額を2,000万円まで抑えられます。これは「実際の市場価格が下がる」という意味ではなく、相続税の計算上の課税対象額が減るという仕組みです。したがって、同じ資産を相続しても、この特例を活用するかどうかで納める相続税の額には大きな差が生じることになります。
ただし、この制度が適用できるのは、被相続人が実際にアパート経営や賃貸マンション経営を行っていた場合に限られ、単なる「駐車場貸し」や一時的な土地貸しなどでは対象外となることがあります。また、相続後も賃貸事業を継続することが条件とされているため、すぐに売却してしまうと適用が認められないケースもあります。
数値例(評価額ベース)
賃貸マンション敷地の評価額が 6,000万円(180㎡) の場合:
- 特例なし → 評価額6,000万円
- 特例あり → 評価額3,000万円(▲3,000万円)
👉 相続税評価額が 3,000万円下がる。
注意点
- 「事業的規模」とみなされることが必要(戸数や規模で判断)。
- 駐車場のみの土地などは対象外になることもある。

③ 🏠 建物に対する特例は限定的
基本は固定資産税評価額
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額をそのまま用います。これは市場価格よりも低めに設定されており、土地と比べると税負担は小さくなりやすいです。
建物構造ごとの耐用年数と評価の特徴
木造住宅は法定耐用年数が短く、築20年以上経つと評価額が数十万円程度まで落ち込むこともあります。したがって、建物が相続税額に与える影響は土地に比べて限定的です。
1. 木造住宅
- 法定耐用年数:22年(木造モルタル造は20年)
- 築年数が経過すると急速に評価額が減少。
- 築20年以上では、評価額が数十万円程度まで落ちることも多い。
👉 相続税評価ではほとんど影響を与えないケースも多い。
2. 鉄骨造(軽量鉄骨・重量鉄骨)
- 軽量鉄骨(厚さ3mm以下):19年
- 中厚鉄骨(3mm超〜4mm以下):27年
- 重量鉄骨(4mm超):34年
- 木造よりも耐用年数が長いため、築後20年でも一定の評価額が残りやすい。
👉 築30年でも建物評価が数百万円残っていることがある。
3. RC造(鉄筋コンクリート造)
- 法定耐用年数:47年
- 減価償却の進み方が緩やかで、築20年〜30年でも相応の評価額が残ります。
- 築30年であっても、評価額が数千万円規模で残っているケースも珍しくありません。
👉 都心のマンションなどでは土地と合わせて評価額が高額になりやすい。
4. SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 法定耐用年数:50年
- RC造よりさらに長持ちする構造で、築30年経過しても高い評価額が維持されやすい。
- 相続税評価でも減価のスピードが遅いため、土地に次いで課税への影響が大きく残る構造といえます。
「貸家建付建物」の評価減
被相続人が生前に所有していた建物を第三者に賃貸していた場合、その建物は相続税の評価上「貸家建付建物」として取り扱われます。通常の自用建物と異なり、そこに借家人(入居者)の権利が存在するため、所有者は自由に使用できない制約を受けています。この制約分を考慮して、評価額から借家権割合(一般的には30%程度)を控除して減額する仕組みになっています。
例
- 建物評価額:1,000万円
- 借家権割合:30%
- 実際の評価額:700万円
④ 区分マンション1室を賃貸に出している場合の扱い
1. 特例との関係
区分マンションを賃貸に出している場合、所有者は自分が住むための専有部分ではなく、第三者に貸している**建物(専有部分)と、その部屋に付随する敷地権(共有持分の土地部分)**を所有していることになります。この敷地権については、相続税の計算において「貸付事業用宅地」に該当すると判断されれば、上限200㎡までの範囲で評価額を50%減額する特例を受けられます。つまり、区分マンションであっても土地部分の権利がある以上、理論上は特例の対象に含まれる可能性があるということです。
2. 実務上の注意点
- 敷地が共有なので、自分の持分はごく小さい。
例:敷地600㎡を30戸で共有 → 1戸の持分は20㎡。 - この「持分面積」を合算して200㎡までが対象。1室だけでは効果はごく限定的。
- 「事業的規模」の要件を満たさないと適用できないことも多い。
3. 結論
- 区分マンション1室でも適用可能な場合はあるが、効果は小さい。
- 規模要件を満たさない場合、対象外になる可能性が高い。
⑤ シミュレーションで理解する
ケース1:自宅と賃貸アパートを所有
- 自宅土地:3,000万円
- 賃貸アパート土地:4,000万円
- 合計:7,000万円
→ 特例適用後
- 自宅:3,000万円 × 20% = 600万円
- 賃貸アパート:4,000万円 × 50% = 2,000万円
- 合計:2,600万円
👉 相続税評価額は 7,000万円 → 2,600万円(▲4,400万円)
※減るのは「課税評価額」であり、相続税額そのものが4,400万円下がるわけではありません。
ケース2:区分マンション1室を賃貸
- 敷地全体600㎡ → 1室持分20㎡
- 評価額:400万円
→ 特例適用後(50%減額)
- 400万円 → 200万円(▲200万円)
👉 相続税評価額が200万円下がるにとどまり、影響は小さい。
配偶者控除による相続税の軽減
1. 配偶者控除とは?
配偶者が相続する財産については、**相続税額の軽減(配偶者控除)**が認められています。これは、残された配偶者の生活を保障するための制度で、非常に大きな優遇措置です。
2. 控除額の内容
配偶者が取得した財産について、次のいずれか多い方まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円 まで
- 法定相続分相当額 まで
つまり、相続財産が多額であっても、配偶者が取得する分については多くの場合で相続税がかからない仕組みになっています。
3. 小規模宅地等の特例との違い
- 小規模宅地等の特例:土地の相続税評価額を下げる制度
- 配偶者控除:配偶者が相続した財産の相続税額を軽減する制度
両者は併用可能であり、例えば「自宅の土地を80%減額したうえで、それを配偶者が相続し、さらに配偶者控除を使う」という形も取れます。
4. 注意点
- 相続税がゼロになった場合でも、配偶者の相続分をきちんと申告する必要がある(申告不要と思い込みやすい点に注意)。
- 二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)では配偶者控除が使えないため、一次相続で全財産を配偶者に寄せすぎると、二次相続で税負担が増えるリスクがあります。
⑦ よくある誤解と落とし穴
- 「マンションを貸していれば自動で半額になる」→ ❌
- 「青空駐車場も対象になる」→ ❌
- 「建物にも特例がある」→ ❌
👉 あくまで土地の評価に対する特例が中心です。
⑧ まとめ
- ✅ 自宅:最大80%減額(330㎡まで)
- ✅ 賃貸用土地:最大50%減額(200㎡まで)
- ✅ 建物:固定資産税評価額ベース、急速に価値減少
- ❌ 建物特例:なし
- ⚠️ 区分マンション1室:敷地持分は対象になるが効果小さい
⑨ 専門家からのアドバイス
相続税評価の特例は大変有効ですが、適用条件を誤解すると「思ったより減らなかった」ということになりがちです。特に区分マンションや駐車場の扱いは判断が難しい分野です。
実際に相続が発生した場合や事前対策を検討する際は、税理士や不動産の専門家に相談し、正しく試算することが不可欠です。
不動産売却・賃貸募集・賃貸管理のお悩みはプロに無料相談!
不動産会社セレクトビジョンにお任せください!
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!




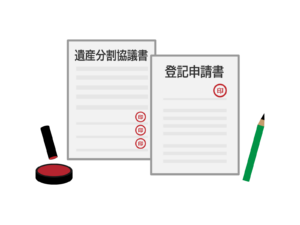


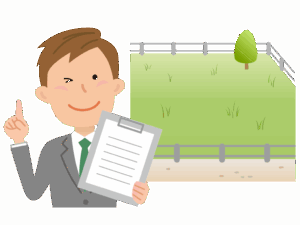

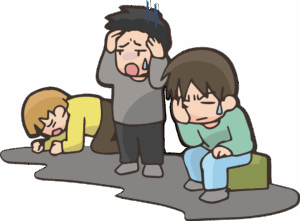


コメント