相続は生前対策が重要!基礎控除と節税ポイントを徹底解説

「相続なんて、自分が亡くなった後に家族が考えればいい」そう思っていませんか?
実は、本当に効果がある相続対策の多くは、生前にしかできません。
相続税の節税、遺産分割のトラブル回避、納税資金の準備…。これらは本人が元気なうちから動かなければ手遅れになってしまうのです。
この記事では、相続の生前対策と亡くなった後の手続きの違いをわかりやすく解説し、さらに「生命保険」を活用した具体的なシミュレーションを紹介します。はじめて相続について考える方でも理解できるように、丁寧に整理しました。
まず知っておきたい「相続税の基礎控除」
相続税がかかるかどうかは、まず 相続財産の総額が「基礎控除」の金額を超えるかどうかで決まります。
基礎控除とは、相続財産から一定額までは税金がかからない仕組みのことで、この枠の範囲内に収まっていれば相続税は発生しません。逆に1円でも超えた部分があれば、その超過分に対して相続税が課されることになります。
基礎控除の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が妻と子ども2人の3人なら、
👉 3,000万円+600万円×3=4,800万円まで非課税。
ポイント
- 財産が4,800万円以下なら相続税はかからない。
- 逆に、1円でも超えると課税対象になる。
- 預貯金・不動産・株式・生命保険金を合算すると、都市部ではすぐ基礎控除を超えるケースが多い。
👉 「うちは関係ない」と思っていても、実際には相続税がかかる家庭は少なくありません。
生前にしかできない5つの代表的相続対策
1. 生前贈与で相続財産を減らす
暦年贈与(毎年110万円非課税)の活用
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額のうち、110万円までが非課税になる制度です。例えば、親から子へ毎年110万円ずつ贈与した場合、贈与税は一切かかりません。
- メリット
- コツコツと長期間にわたり贈与を続ければ、相続財産を大きく減らせる。
- 相続時の基礎控除と併用することで、課税対象額をさらに圧縮できる。
- 贈与を受けた子が早い段階で資金を活用できる(住宅取得・教育費など)。
- 落とし穴・注意点
- 贈与したつもりでも「贈与契約書」や「資金移動の証拠」がなければ、税務署から「実態は贈与ではなく相続財産」と判断される可能性がある。
- 「名義預金」と呼ばれるケースに注意。たとえば子ども名義の口座に親が勝手に入金しているだけでは贈与と認められない。
- 相続開始前3年以内の贈与は「持ち戻し」とされ、相続財産に合算される。つまり、亡くなる直前の贈与は節税効果が薄い。
👉 暦年贈与は「時間をかけて計画的に」行うことがカギ。10年、20年と継続すれば、数千万円単位で課税対象を減らすことも可能です。
相続時精算課税制度(特別控除2,500万円)の活用
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与が非課税になる仕組みです。60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する場合に利用できます。
- 仕組み
- 2,500万円まで贈与税はかからない。
- 超過分は一律20%の贈与税が課税される。
- ただし「相続時精算」という名前のとおり、将来の相続時に贈与分を相続財産に合算して相続税を計算する。
- メリット
- 大きな財産を一度に移転できる。
- 生前に子や孫に資産を渡し、住宅購入資金や事業承継などに活用してもらえる。
- 贈与時点では贈与税がかからないため、資金移動のハードルが低い。
- デメリット・注意点
- 将来の相続時に合算されるため、結果的に節税効果は限定的。
- 一度この制度を選択すると暦年贈与(毎年110万円非課税)は使えなくなる。
- 贈与後に財産が値上がりすると、増加分も含めて相続財産として課税対象になる。
- うっかり「節税になる」と勘違いして利用すると、逆に不利になることも。
👉 相続時精算課税制度は「節税」目的ではなく、財産を早めに子や孫に移転するための制度と考えた方が適切です。特に「住宅資金援助」「事業承継」「将来資産価値が下がる不動産を早めに移転」などに活用すると効果的です。
2. 遺言書の作成で争いを防ぐ
相続において「遺言書があるか・ないか」で、手続きの流れも相続人同士の関係も大きく変わります。
遺言書は本人が生きている間にしか作れないため、生前対策の中でも最も重要なものの一つです。
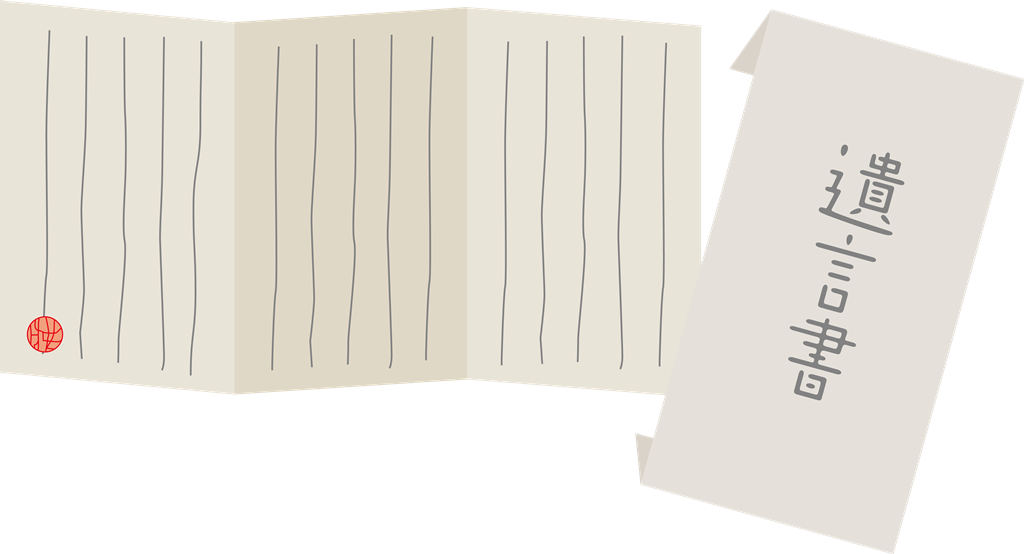
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
- 検認不要
遺言書の中でも、公正証書遺言は家庭裁判所での「検認手続き」が不要です。相続開始後すぐに執行できるため、手続きがスムーズに進みます。 - 法的効力が強い
公証人が関与して作成するため、形式不備で「無効」となるリスクが極めて低い。文字や日付の書き間違い、押印漏れといったミスも防げます。 - 原本は公証役場で保管
紛失や改ざんの心配がないのも大きな安心材料です。
👉 相続人同士のトラブルを最小限に抑えたいなら、公正証書遺言が最も確実な方法といえるでしょう。
自筆証書遺言と法務局保管制度
自筆証書遺言は、本人が全文を手書きで作成する遺言書です。
- メリット
- 費用がかからない(紙とペンがあれば作れる)。
- 思い立ったときにすぐに作成できる。
- デメリット
- 字句の不備、日付の欠落、押印忘れなどで無効になることが多い。
- 紛失や改ざんのリスクがある。
- 相続開始後は家庭裁判所で「検認」が必要で、手続きに時間がかかる。
これを補う制度が「法務局での自筆証書遺言保管制度」です。
- 遺言書を法務局に預けておけば、相続人が簡単に検索・取得できる。
- 改ざんや紛失の心配がなく、検認も不要になる。
- 作成は自筆である必要がありますが、保管によって信頼性がぐっと高まります。
👉 費用を抑えつつ、遺言の安全性を確保したい場合に有効な制度です。
遺言がない場合のリスク
もし遺言がないまま相続が始まると、財産の分け方は法定相続分に従うか、**相続人全員の合意(遺産分割協議)**で決めることになります。
- 相続人が多いほど、全員の合意形成は難しい。
- 一人でも反対すれば協議は成立しないため、遺産分割が長期化する。
- 特定の財産(不動産・事業用資産など)が絡むと「誰が相続するか」で争いになりやすい。
実際に相続トラブル(いわゆる「争族」)の大半は、遺言書がなかった家庭で発生しています。仲が良い家族でも、財産が絡むと意見が対立することは珍しくありません。
👉 「自分の家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、将来トラブルになる可能性はゼロではありません。遺言書を残すことは、家族への最後の思いやりと言えるでしょう。
3. 生命保険の活用
相続対策の中で、もっとも取り入れやすく効果が大きいのが「生命保険の活用」です。単なる保障のためではなく、相続税の節税・遺産分割の円滑化・納税資金の確保という観点で非常に重要な役割を果たします。
生命保険の非課税枠を利用できる
死亡保険金には、独自の非課税枠が設けられています。
計算式:500万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が妻と子ども2人なら、
👉 500万円 × 3人=1,500万円が非課税。
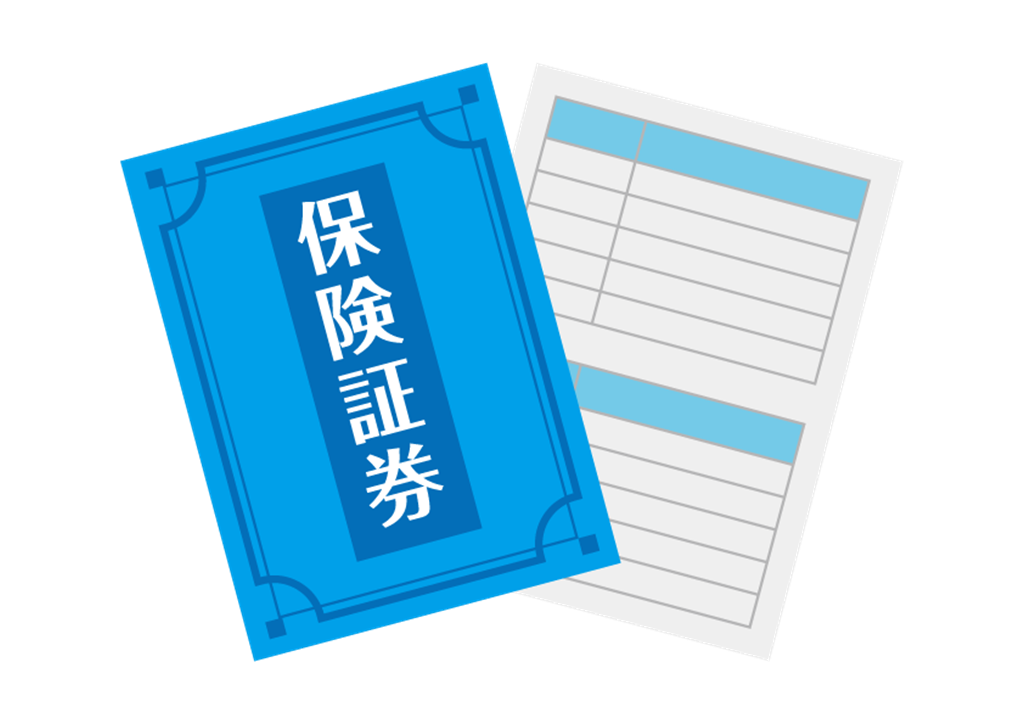
つまり、5,000万円の保険金を受け取ったとしても、そのうち1,500万円は相続税の課税対象から除外されます。
これは相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)とは別枠なので、ダブルで控除を受けられる点が大きなメリットです。
受取人を指定できる=財産分割の調整が可能
相続財産の多くは「誰がどの財産を受け取るか」で揉めやすいものです。特に不動産が中心の場合、現金に比べて分割が難しくトラブルの火種になりがちです。
生命保険金は、受取人を事前に指定できるという特徴があります。
- 妻を受取人に指定すれば、生活資金を確実に残せる。
- 子どものうち一人を受取人に指定すれば、他の相続財産とのバランス調整に使える。
また、生命保険金は「受取人固有の財産」とされ、基本的には遺産分割協議の対象になりません。そのため、スムーズに受取人の手元に現金を残すことができます。
納税資金を準備できる
相続税は原則として「現金で一括納付」しなければなりません。
不動産や株式ばかりで現金が少ない家庭では、「相続税が払えないから不動産を急いで売却する」という事態に陥ることがあります。
このようなケースでも、生命保険を活用すれば確実に現金を準備できるため、相続人が困らずに済みます。
特に地主や不動産オーナーの方にとっては「納税資金対策」としての生命保険は非常に有効です。
相続トラブル防止にも役立つ
生命保険金は、受取人を明確にしておけば「誰がいくらもらうか」がはっきりします。
これにより、相続人同士の不満を軽減し、相続トラブルの防止につながります。
例えば…
- 妻に保険金を残すことで、生活の安定を確保できる。
- 子どもの一人に事業を継がせたい場合、その子に保険金を集中させて株式の偏りを調整できる。
「公平」と「納得感」を両立させやすいのが生命保険の強みです。
生前にしか契約できない点に注意
保険契約や受取人の指定は、本人が生きている間にしかできません。
亡くなった後に「やっぱり受取人を変えたい」「保険金を増やしたい」と思っても、それは不可能です。
だからこそ、早めに準備しておくことが相続対策の要となります。
不動産売却・賃貸募集・賃貸管理のお悩みはプロに無料相談!
不動産会社セレクトビジョンにお任せください!
4. 不動産や株式の名義整理
相続財産の中で特にトラブルになりやすいのが「不動産」と「株式」です。
現金のように分けやすい資産ではないため、生前に名義を整理しておくことが大切です。

不動産の名義整理の重要性
日本の相続トラブルで最も多いのは、不動産をめぐる争いです。
- 共有名義の問題
親の不動産を複数の子どもで相続すると、共有名義になります。一見公平に見えますが、共有名義は非常に扱いづらいのが実態です。- 売却するには共有者全員の同意が必要
- 修繕・建替えのときに意思決定が進まない
- 将来さらに相続が起きると、名義人がどんどん増えて権利関係が複雑化
こうした状況になると「不動産が塩漬け状態」になり、利用も売却もできず、相続人の負担だけが増えるケースが多発します。
- 名義変更の遅れ
不動産の名義変更(相続登記)は2024年から義務化されました。放置すると罰則(過料)の対象になり、さらに第三者との取引もできなくなります。
👉 生前のうちに「誰に相続させるのか」を決め、遺言や贈与で名義を整理しておくことが、家族の負担を減らす最大の対策です。
株式(自社株・非上場株)の名義整理の重要性
事業を営んでいる家庭にとっては、株式も大きな相続リスクとなります。
- 自社株が分散すると経営に支障
会社の株式を複数の相続人に分けてしまうと、議決権が分散して経営判断に支障が出ます。場合によっては、後継者が十分な持ち株比率を持てず、経営権を失うリスクもあります。 - 株式の評価額が相続税に直結
非上場株は税務上の評価が複雑で、想定以上に高額評価されることも。事業用資産を承継するつもりが「相続税が払えない」といった事態に陥ることもあります。 - 事業承継税制の活用
一定の要件を満たせば、自社株の相続税や贈与税を猶予・免除できる「事業承継税制」もあります。これは生前の準備が前提となるため、早めの対策が必要です。
👉 株式承継は「誰が会社を引き継ぐのか」「どのように株式を集中させるのか」を生前に設計しておくことが欠かせません。
生前に整理しておくメリット
- 相続発生後の手続きがスムーズになり、家族が困らない
- 不動産を売却・活用しやすくなる
- 株式の集中で後継者の経営権を安定させられる
- 相続人同士のトラブルを未然に防げる
👉 特に「不動産が複数ある」「事業を営んでいる」家庭では、この生前整理が相続対策のカギになります。
5. 家族への意思表示
相続対策というと「税金」や「書類」のイメージが強いですが、実は家族に自分の意思をしっかり伝えておくことも非常に大切です。
遺言書や生命保険だけでは補いきれない部分を、本人の言葉で補っておくことでトラブルを大幅に防ぐことができます。

なぜ意思表示が大切なのか
- 遺言書だけでは「なぜそうしたのか」の理由が書かれていないことが多い。
- 財産を多くもらった相続人ともらえなかった相続人の間で「不公平感」が生まれやすい。
- 本人の意向がわからないまま相続人だけで話し合うと、感情的な対立に発展することがある。
👉 本人が生きている間に「なぜそう分けたいのか」を説明しておけば、相続人は納得感を持ちやすくなります。
意思表示の方法
- 家族会議を開く
- 年に1度、財産や今後の考え方について家族で話し合う。
- 「この不動産は長男に継がせたい」「生活のことを考えて妻には現金を残す」など、本人の希望を直接伝える。
- エンディングノートを残す
- 法的効力はないが、財産一覧や想いを書き残すことで家族にとっての道しるべになる。
- 遺言書とセットで残すと効果的。
- 遺言書に付言事項を加える
- 「なぜこのように遺産を分けたのか」という理由を簡単に書き添える。
- 法的拘束力はないが、家族が遺志を尊重する上で大きな役割を果たす。
意思表示がないとどうなるか(トラブル例)
- 遺言書に「不動産は長男に相続させる」とだけ書かれていたが、その理由が分からず、他の兄弟が「不公平だ」と反発 → 相続協議が長期化。
- 父親が「妻には十分な現金を残す」と考えていたが伝えないまま亡くなり、遺産分割で妻の取り分が少なくなり生活に不安が生じた。
👉 こうしたトラブルは、本人が生前に一言でも説明しておけば防げた可能性が高いのです。
まとめ:相続は“生前の準備”で大きく変わる
相続は「亡くなってから家族が対応すればいいもの」と思われがちですが、実際には 本当に効果のある相続対策の多くは、生前にしかできません。
- 生前贈与では、暦年贈与(毎年110万円非課税)や相続時精算課税制度(特別控除2,500万円)を活用し、時間をかけて財産を移転できる。
- 遺言書を残しておけば、相続人の合意を待たずにスムーズな分割が可能。公正証書遺言や法務局保管制度を使えば、効力や安全性も確保できる。
- 生命保険は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できるだけでなく、納税資金や生活資金の確保、分割の公平性にも役立つ。
- 不動産や株式は共有や分散が大きなトラブルの火種。生前に名義を整理しておくことで、将来の混乱を防げる。
- 家族への意思表示は「なぜこのように分けるのか」を本人が伝えること。遺言書では伝わらない“想い”を残すことで、争族を未然に防げる。
これらの準備を何もしなければ、残された家族は 遺産分割協議や相続税申告といった「手続き」しかできず、節税やトラブル防止の工夫はもう不可能です。
今回のシミュレーションでも、生命保険の非課税枠や配偶者控除を活用した結果、相続税が大幅に軽減できることがわかりました。逆に何も準備していなければ、数十万円〜数百万円の税負担やトラブルが現実となります。
👉 相続は亡くなった後ではなく、生前に準備してこそ家族を守れる。
これこそが「相続は亡くなる前にしかできない対策がある」という言葉の意味なのです。
不動産売却・賃貸募集・賃貸管理のお悩みはプロに無料相談!
不動産会社セレクトビジョンにお任せください!
賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。
「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。
東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。
地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。小さなお悩みでも構いません。
誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対応エリア
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区
新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市
※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!




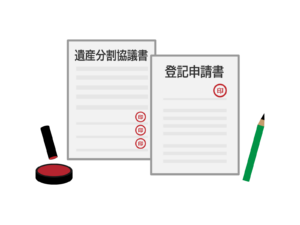


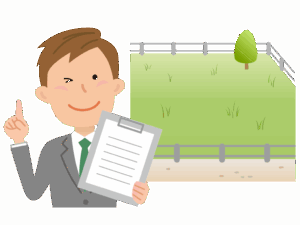


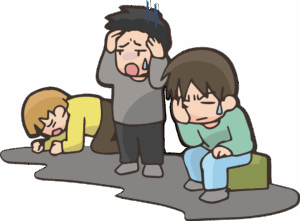

コメント